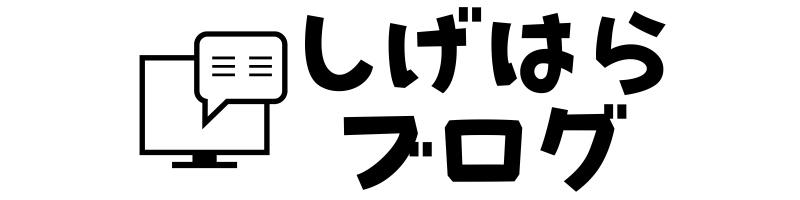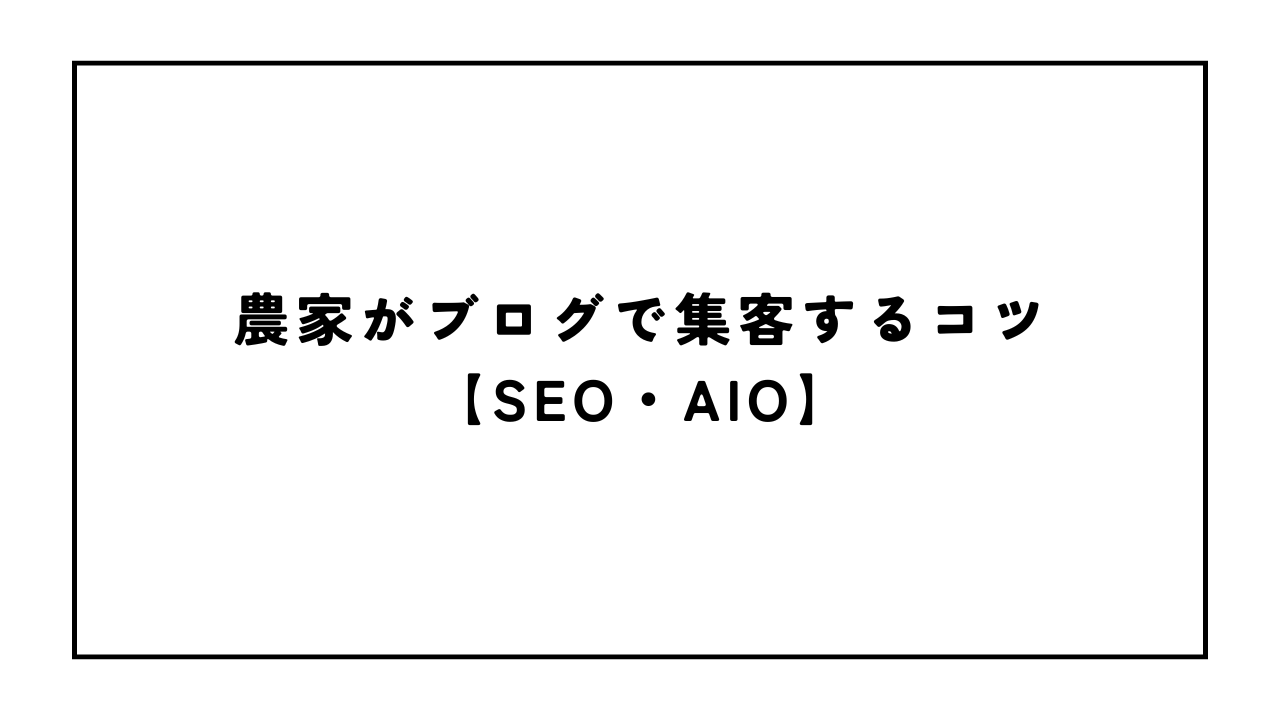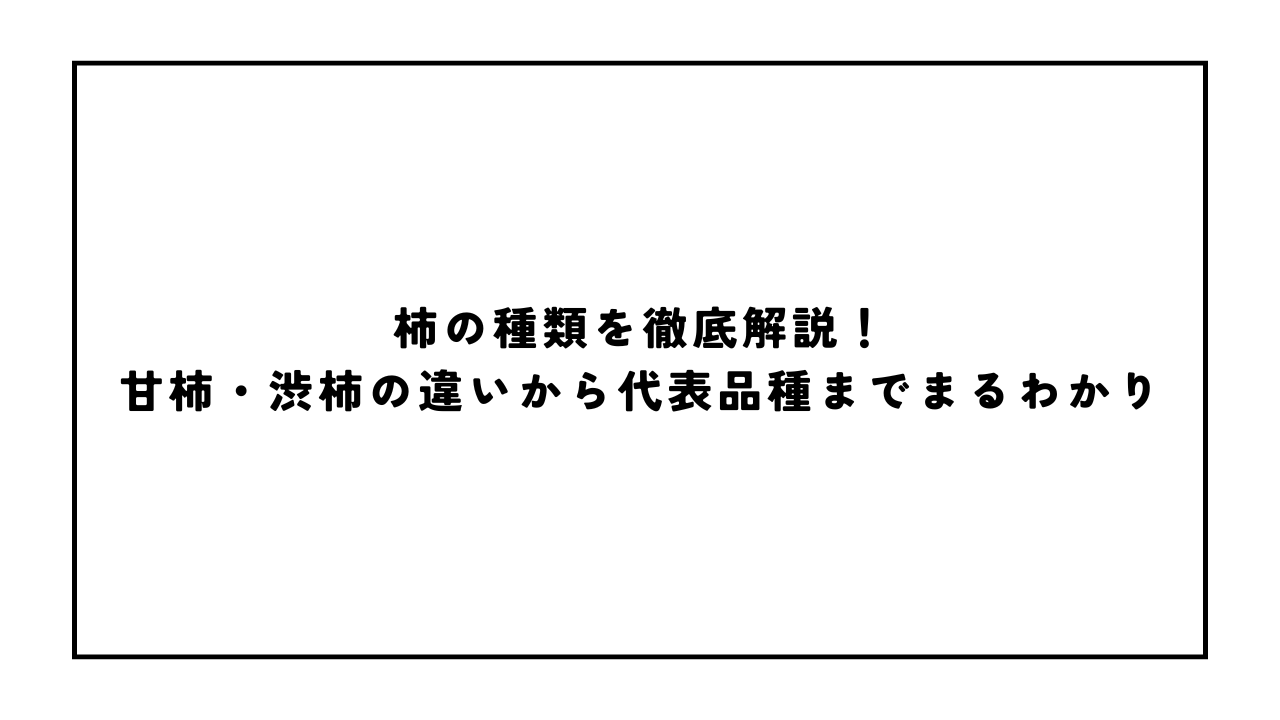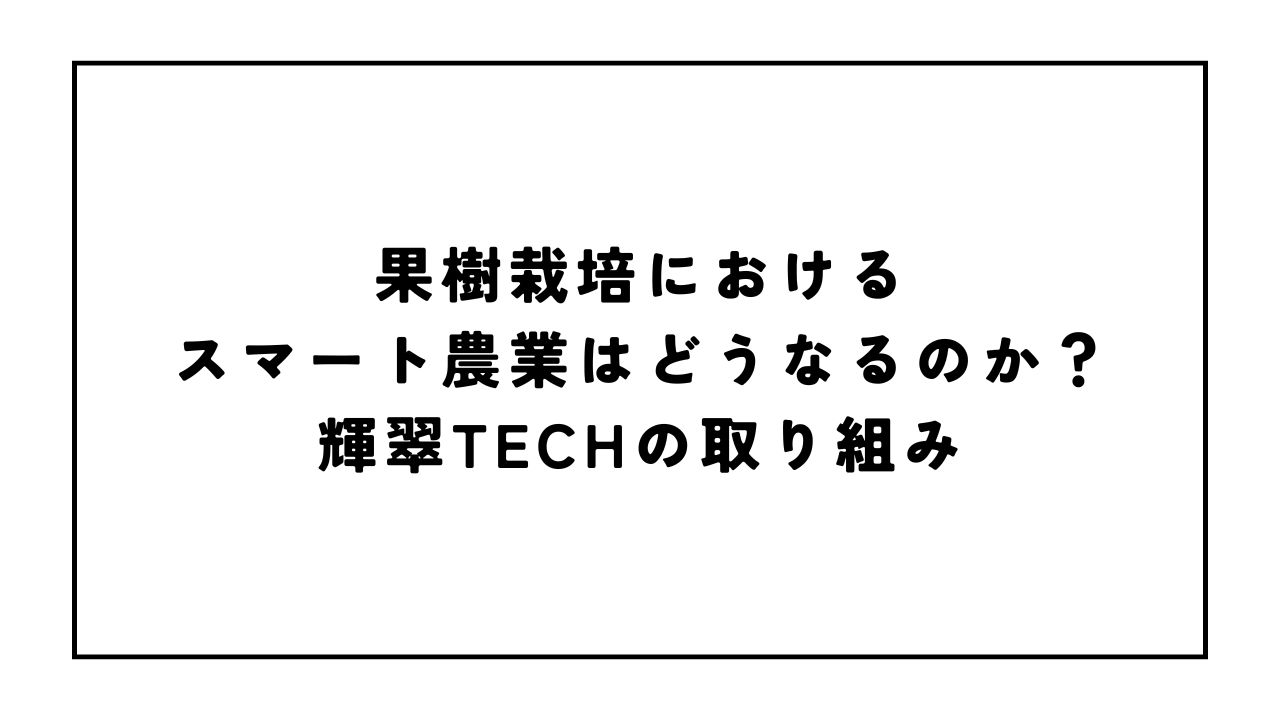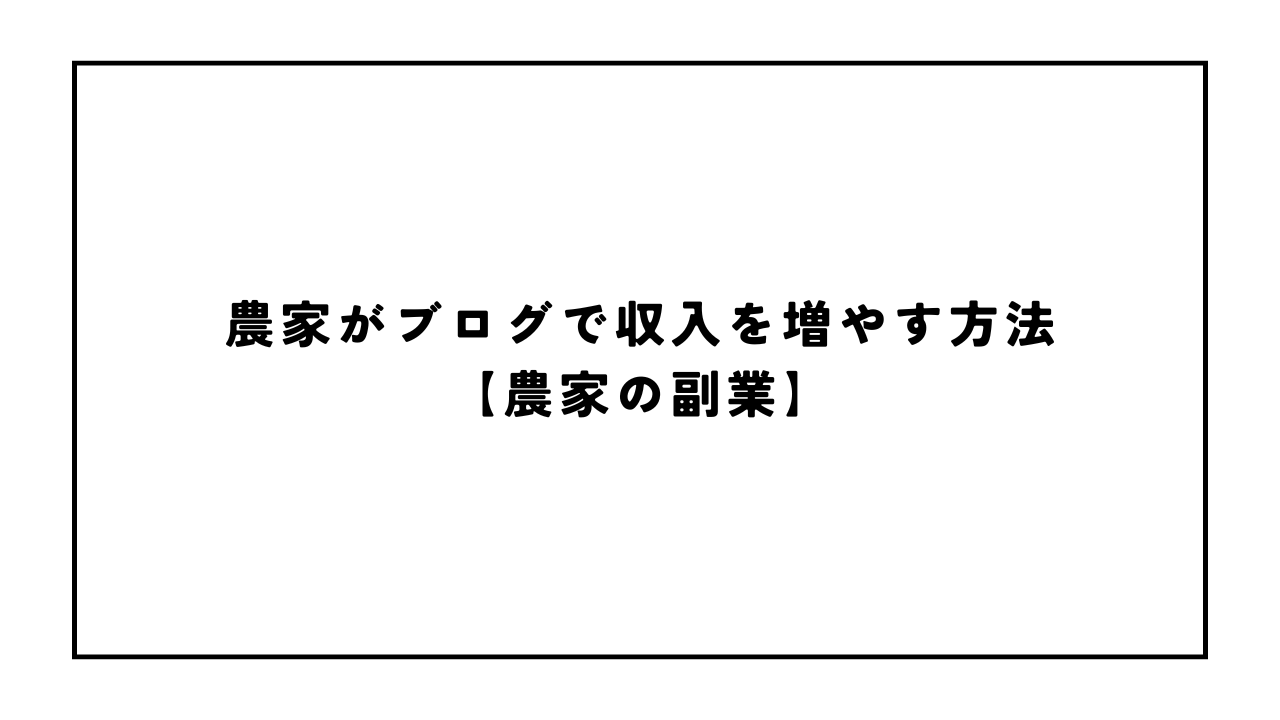農福連携とは?【経験談】障がい者雇用の課題
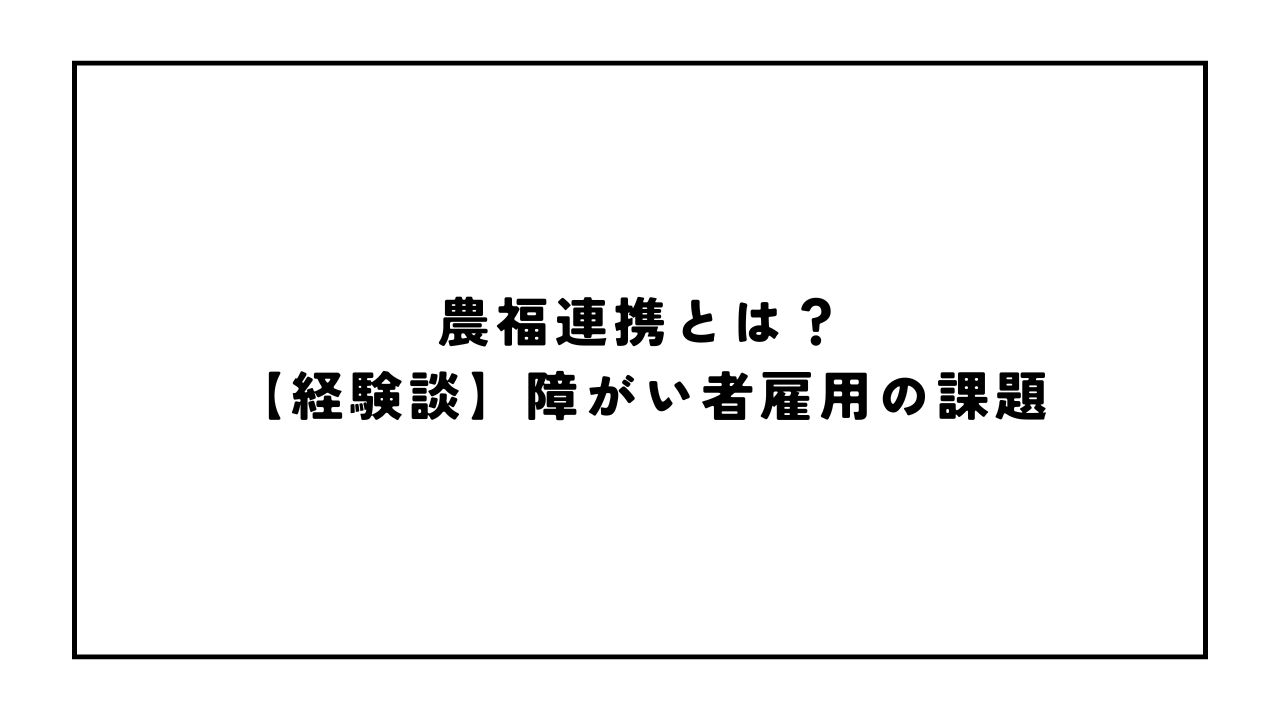
農福連携とは、農業と福祉を組み合わせた取り組みで、障がい者の就労支援と農業の人手不足解消を目指すものです。
全国で導入が進んでいますが、実際に農福連携に取り組むと、さまざまな課題に直面することもあります。
私自身、農福連携で障がい者雇用を経験し、その中で感じた課題や工夫した点についてお伝えします。
また、農福連携の成功事例として静岡県の京丸園を紹介し、どのような作物が適しているのかも考えていきます。
1. 農福連携とは?
1-1. 農福連携の目的
農福連携は、障がい者に働く機会を提供するとともに、農業における慢性的な人手不足を解決することを目的としています。
- 障がい者にとって「適度な運動」「社会参加の機会」を提供できる
- 農業側は「労働力確保」「地域との関係強化」が期待できる
- 国や自治体も支援を進めており、助成金制度がある
1-2. 全国での取り組み
日本各地で農福連携が進められており、特に施設野菜・ハウス栽培などでは成功しているケースが多いです。
もともと農業法人ではない企業が新事業として、福祉施設と協力し農福連携を前提とした施設農業に取り組む事例も増えています。
2. 実際に障がい者雇用をして感じた課題
2-1. 作業のマッチングが難しい
農作業は多岐にわたりますが、すべての作業が障がい者に適しているわけではありません。
- 適している作業:苗の植え付け、収穫、袋詰め、シール貼りなど
- 難しい作業:重量物の運搬、天候に左右される作業、判断力が求められる選別作業など
2-2. 継続的なサポートが必要
- 仕事の流れを細かく説明し、シンプルな工程にする
- 判断が必要ないように機械や器具を導入する
- 支援者(福祉施設スタッフ)との連携が不可欠
2-3. コミュニケーションの壁
障がい者の中には、言葉での指示が伝わりにくい人もいます。そのため、
- 写真付きマニュアルの作成
- 手順を番号化し、視覚的に理解しやすくする
- 数字など定量的な指示をする
といった工夫が必要です。
また農家と障がい者の間に入る施設スタッフの農業への理解も大きなポイントになります。
2-4. 人手不足解消にはすぐにはつながらない
障がい者雇用を導入すれば、すぐに労働力として機能するわけではありません。
- 作業の習熟に時間がかかる
- マンツーマンのサポートが必要な場合もある
- 急な体調不良や欠勤があることを想定する必要がある
2-5. 周囲の理解が不可欠
家族・地域・農業関係者の理解がないと、長期的な取り組みが難しくなります。
農家側からすると一般的なパートさんを雇うよりも雇用に関して勉強したり、気遣いが必要になります。
- 「なぜ障がい者を雇うのか?」を明確に伝える
- 一緒に働くスタッフの理解を得る
- 地域の福祉施設と連携し、サポート体制を整える
3. 農福連携の成功事例:静岡県の京丸園
静岡県浜松市の京丸園は、農福連携の成功事例として全国的に知られています。
3-1. 京丸園の取り組み
- 水耕栽培による葉物野菜の生産を中心に展開
- 京丸姫シリーズとしてブランド化
- 作業内容を細かく分け、それぞれに適した工程を担当
3-2. なぜ成功したのか?
- 環境が整ったハウス栽培:気候の影響を受けにくく、作業しやすい
- 細分化された作業工程:植え付け、収穫、包装など適性に応じた作業ができる
- ブランド化:スーパーや飲食店と直接契約し、安定した販路を確保
社長の鈴木さんの講演で実際に話されていたのは、トレーを清掃する際に「綺麗にしといて」だけだと1枚をずっと洗っていたとのことです。
具体的に何回こすってくださいと指示したり洗浄する機械を導入したりしたそうです。
こういった取り組みは他のパートさんにもプラスに働きます。
これは指示の苦手な農家にとって重要な視点かもしれません。
4. 作物による農福連携の適性
すべての作物が農福連携に向いているわけではありません。
作業のしやすさ、リスク管理のしやすさを考慮すると、以下のような分類ができます。
安定して雇用するには年中仕事があることも重要です。
4-1. 農福連携に適した作物
- レタス・小松菜・ほうれん草(葉物野菜):軽作業が中心で、作業が単純化しやすい
- ミニトマト・いちご:収穫が簡単で、障がい者でも対応しやすい
- ハウス栽培のハーブ類:天候の影響を受けにくく、安定した作業が可能
4-2. 農福連携が難しい作物
- 米・麦・大豆(大規模栽培作物):機械化が進んでおり、障がい者の作業を組み込むのが難しい
- 果樹(柿・ぶどう・りんごなど):剪定や収穫が技術を要し、作業負担が大きい
- 露地野菜(じゃがいも・さつまいもなど):土を掘り起こす作業が体力的に厳しい
5. 農福連携の可能性と今後の課題
5-1. 成功の鍵
- 適した作物、作業を用意する(単純作業の割合を増やす)
- 施設と連携し、サポート体制を整える
- 販路を確保し、継続的な収益化を目指す
5-2. 今後の課題
- 農福連携に適した作物の選定が重要
- 障がい者だけでなく、関わるすべての人の理解を深める
- 農業経営者が障がい者雇用のノウハウを学ぶ機会を増やす
6. まとめ
農福連携は、農業と福祉をつなぐ重要な取り組みですが、単に「障がい者を雇えば解決する」ものではありません。成功するためには、
- 適切な作業を準備する
- 施設と連携してサポート体制を整える
- 地域や企業(販売先含)とのつながりを作る
といった工夫が必要です。農福連携は可能性のある取り組みですが、成功には慎重な準備と継続的な努力が求められます。