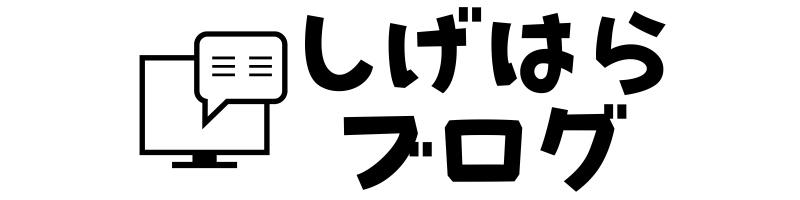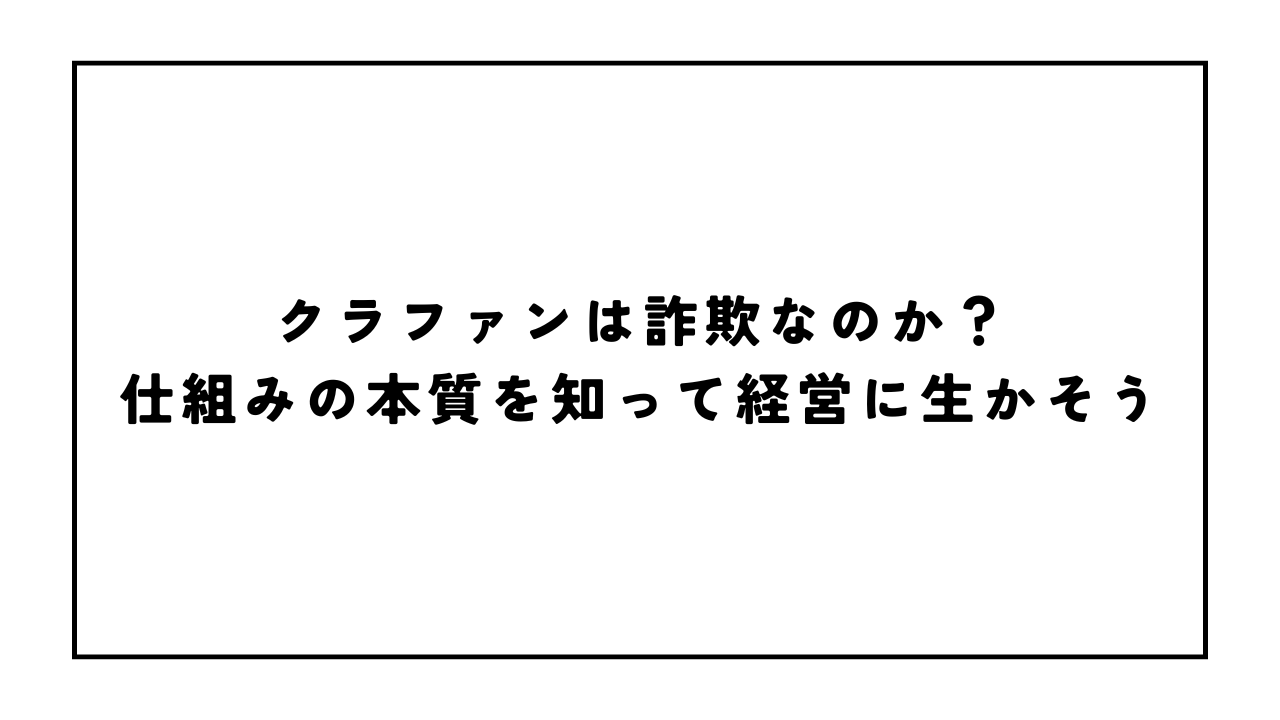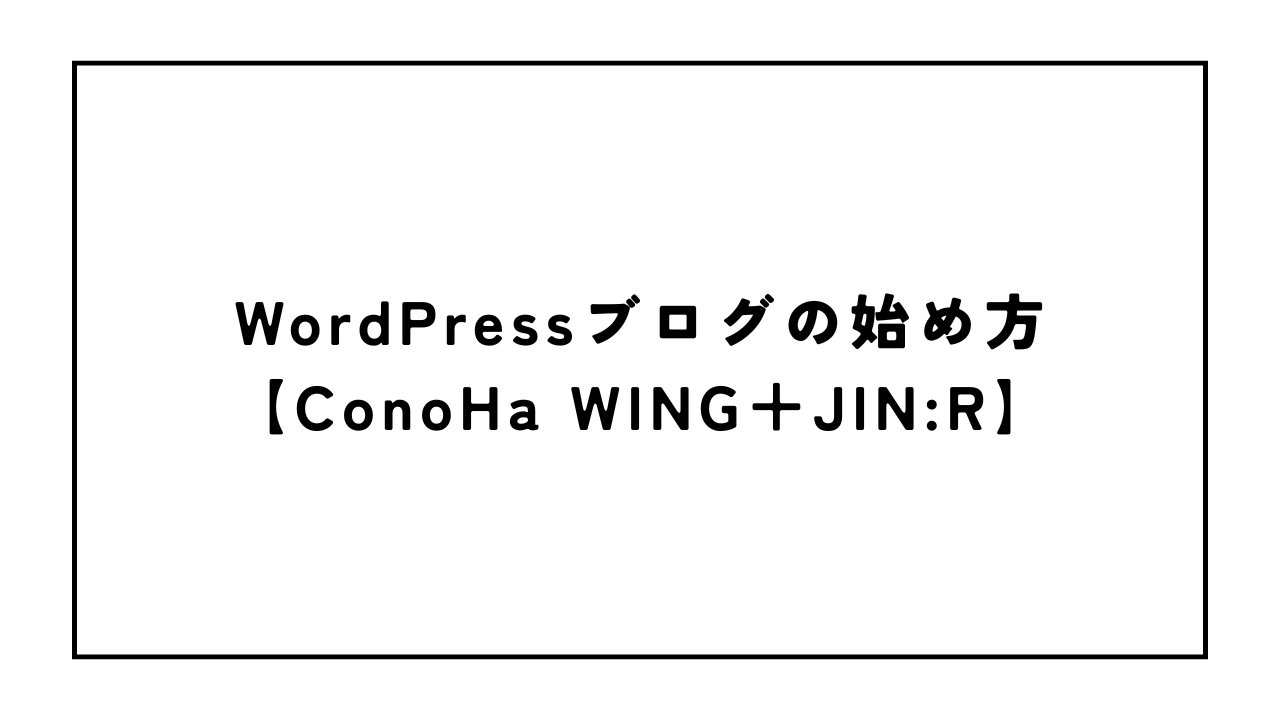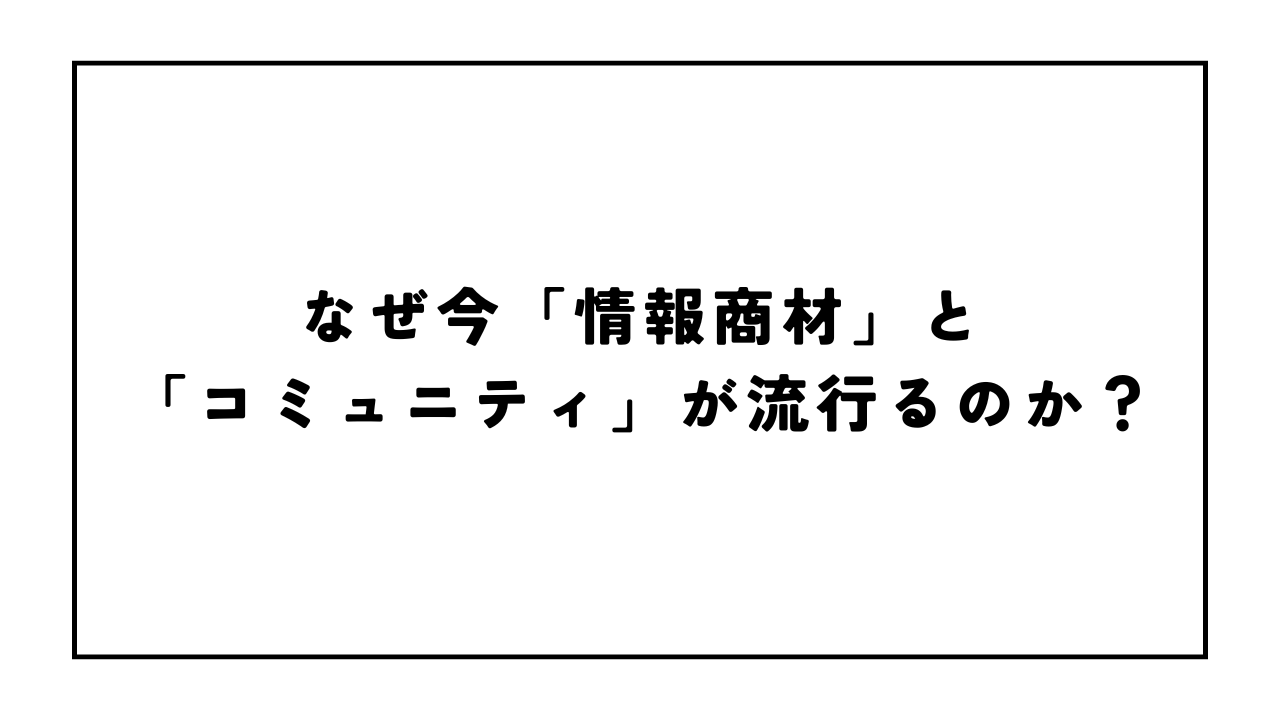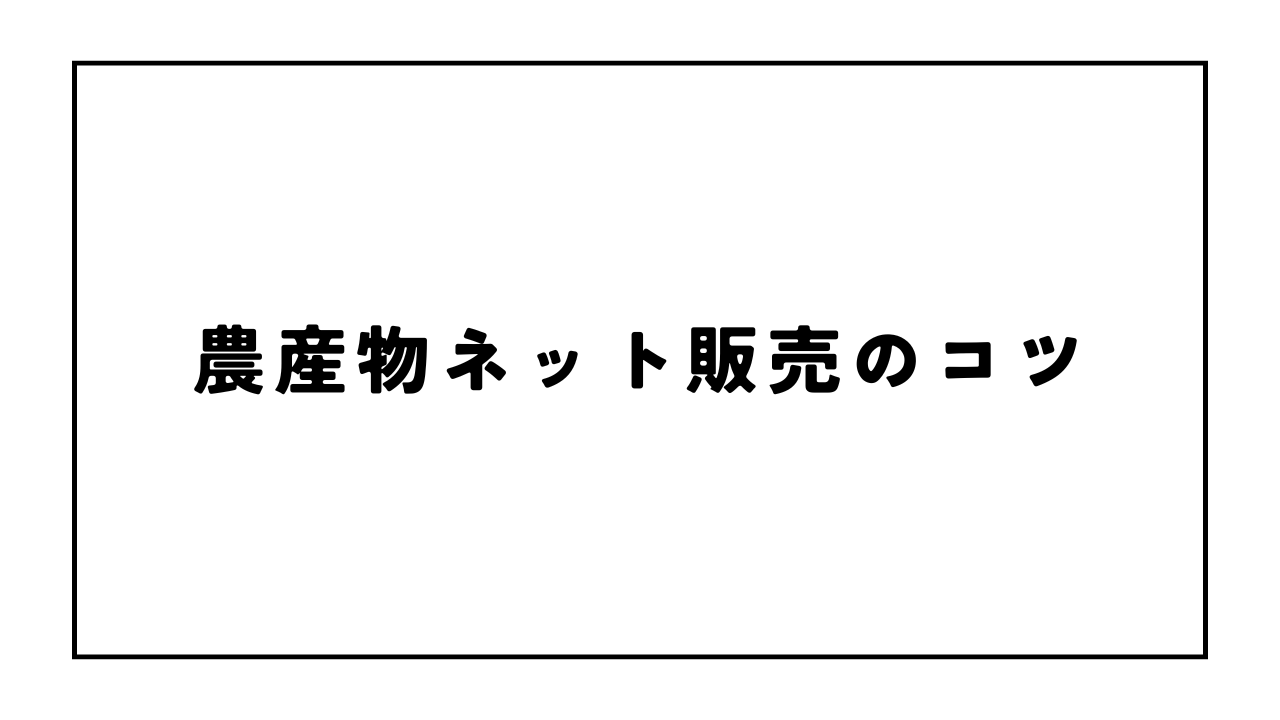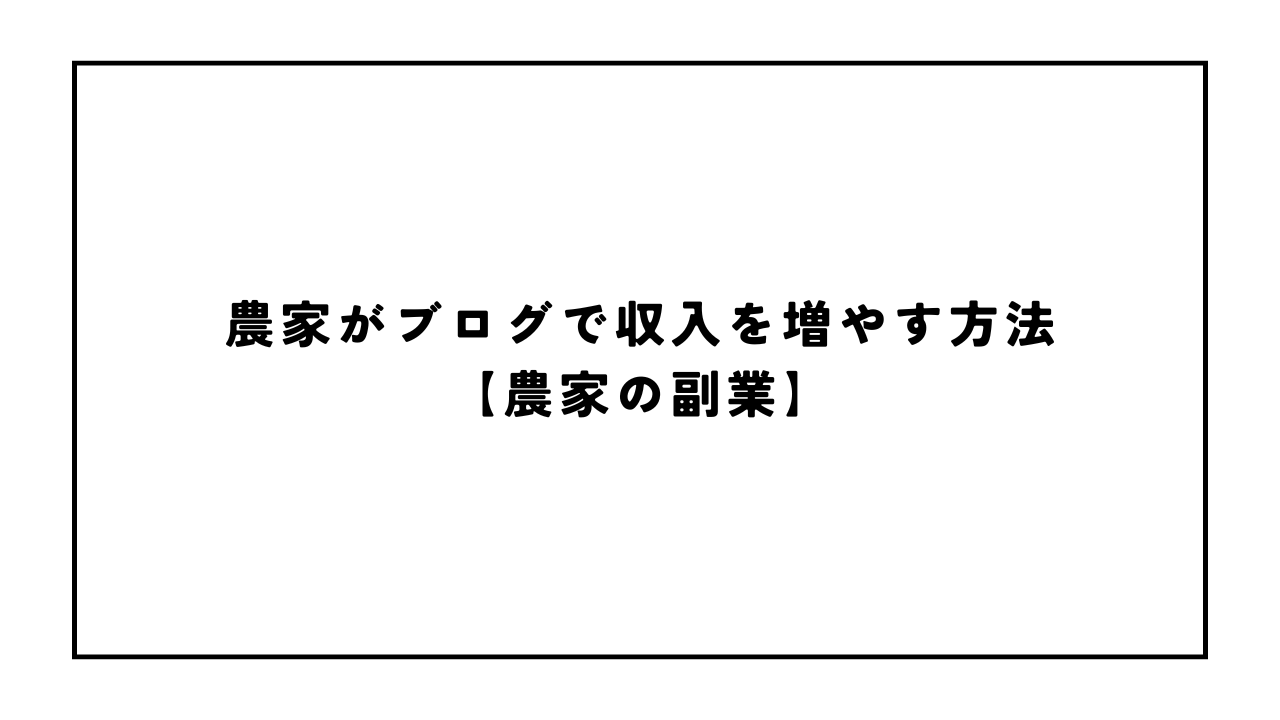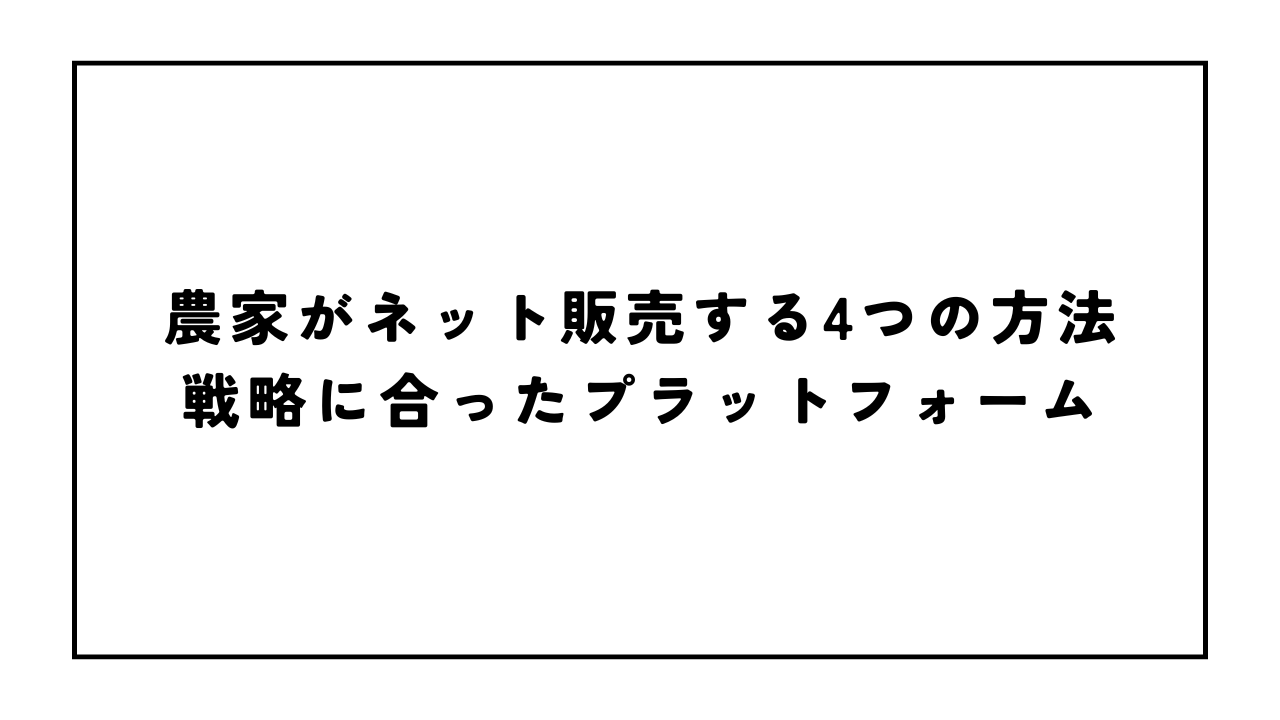コンテンツリパーパスとは?複数 SNSを効率よく運用する方法
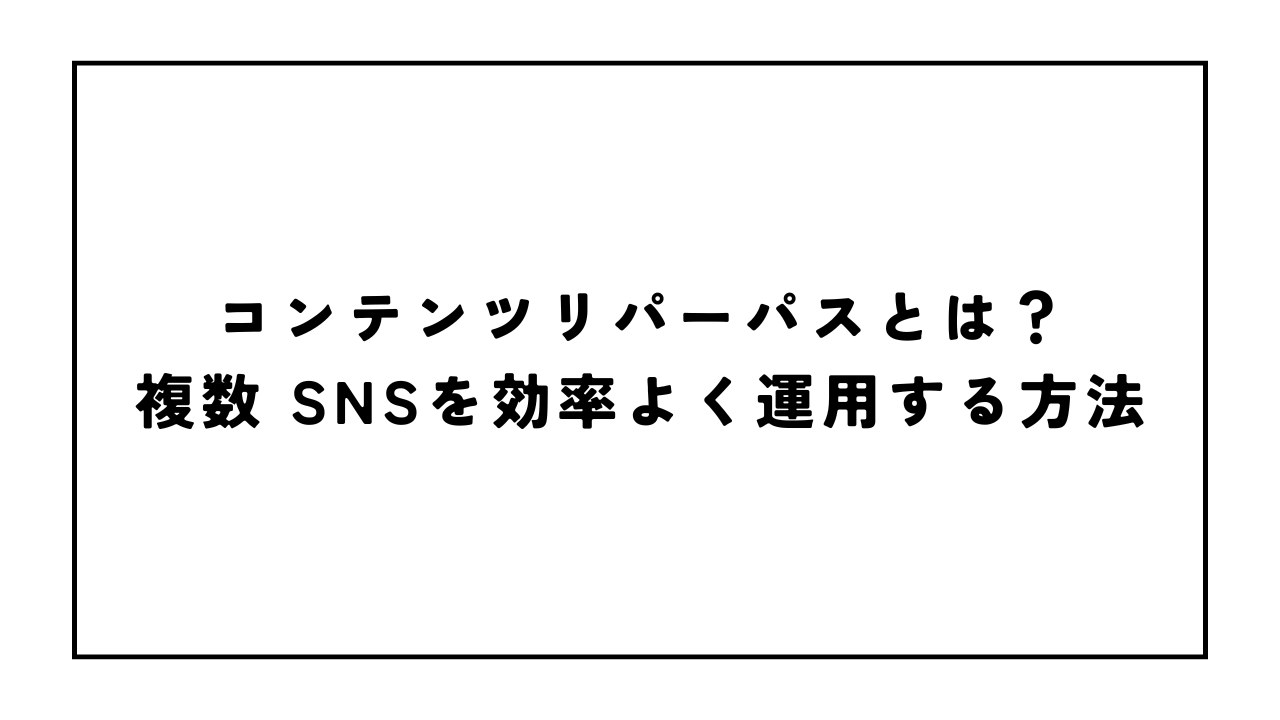
「宣伝に SNS を使いたいけど、X に Instagram、TikTok、YouTube… 数が多すぎて手が回らない──」
そんな悩みを抱える店舗オーナーさんや経営者はきっと少なくないはずです。
ポイントは 「どれを選ぶか」よりも「どうやって労力を抑えて多くのSNSを使うか」だと思います。
鍵を握るのが コンテンツの再利用=コンテンツリパーパス)。
一つの投稿ネタを切り分け&再編集して、複数SNSへスムーズに展開するワザです。
「宣伝に時間はかけられない、でも集客は伸ばしたい」という方の悩みを解決するきっかけにしてもらいたいです。
コンテンツ・リパーパスとは?
コンテンツリパーパスとは、複数の SNS を効率よく運用するための「コンテンツ再利用」戦略です。
SNS ごとに別々のネタを用意するのではなく、ひとつの情報をフォーマットだけ変えて各プラットフォームに展開するイメージになります。
連続起業家のけんすうさんは、この手法を「コンテンツリパーパス」と名付け、下記の記事で詳しく解説しています(後半は有料)。
とても実用的な内容なので、ぜひ課金して他の記事も読んでみてください。
けんすうさんの考え方をベースに、僕なりに最適化したコンテンツ再利用(リパーパス)戦略を具体的に紹介していきます。
なぜ複数のSNSをやるべきなのか
お客さんが情報を得る場所は、人によって驚くほど違います。
例えば、20代はTikTokやInstagramに張り付いている一方、30〜 40 代はYouTubeの解説動画や X(旧 Twitter)の速報を好む。
そんな具合に、利用するSNSは年代や目的で分散しています。
もし 1 つのサービスだけに宣伝を絞ってしまうと、そもそもそこへ来ない層には永遠に届きません。
だからまずは「接触できる入り口を増やす」ことが大切です。
もうひとつ見逃せないのが アルゴリズム変更のリスク です。
タイムラインの仕様が変わったり、リーチを抑えるルールが導入されたりすると、昨日まで伸びていた投稿が急に誰にも届かなくなることがあります。
複数の SNS に情報を置いておけば、片方が不調でも別のチャネルがクッションになり、急激な集客ダウンを防げる―いわば“保険”の役割を果たしてくれます。
さらに、購入に至るまで複数のタッチポイントを踏むケースが増えています。
たとえば「TikTok で商品を知り、X で評判を確認し、最後は YouTube のレビューで背中を押されて購入」という流れです。
あらかじめ多チャネルで情報を用意しておくほど、こうした自然な深掘りにスムーズに対応できます。
とはいえ「じゃあ全部で別々のネタを作ろう」と考えると、人手も時間も足りません。
そこで役に立つのが コンテンツリパーパス という考え方です。
長尺動画や音声など“母コンテンツ”を 1 本作り、そこから文字起こし・短尺動画・要約ポストを切り出して各 SNS に展開すれば、作業量をほとんど増やさずに露出だけを広げられる。
要するに、どの SNS を使うかより「どうやって同じネタを効率良く回すか」がこれからの勝ち筋。
次章では、そのコンテンツリパーパスを使って “1 ネタを 7 チャネルに展開する” 手順を具体的に考えていきます。
1ネタで 7 SNSに投稿する具体例
具体的に1つのネタを7つのSNSに投稿する例を考えていきます。
動画で情報発信を収録します。長めの動画のイメージです。
録った素材を文字起こしし、見出し構成をAIで直して長文記事として公開します。
記事の各見出しごと要約し、4〜5ポストに。最後にブログへのリンクを置いてもいいです。
短いキャプションにまとめ、サムネや写真と合わせて投稿。
尺動画の見どころを縦型 60 秒にまとめ、字幕を付けてショート動画として投稿。
動画の音声だけを整えてポッドキャストとして配信すると、通勤・作業中に“ながら聴き”したい層に届きます。
例えばこのように展開することも出来ます。
もちろん最初の動画をそのままYouTubにあげたり、ライブ配信で行うのもありだと思います。
すべてのSNSに展開しなくても情報によっていくつかのSNSに絞って投稿するという戦略もとれます。
コンテンツを再利用するための考え方とポイント
ここまで読んで「1本のネタをうまく使えば、こんなにも広く発信できるんだ!」と感じた方も多いかもしれません。
ですが、いきなりたくさんのSNSに展開しようとすると、ツールの使い方やフォーマットの違いに戸惑ったり、作業の多さに気が引けたりすると思います。
すべてのSNSに出す必要はありません
まず大前提として、「全部のSNSで投稿しなきゃ」と気負う必要はありません。
コンテンツリパーパスの目的は、“ラクに発信量を増やす”こと。
自分が普段使っているSNSや、お客さんがよくいる媒体を中心に、やれる範囲で展開していくというのが現実的なスタートです。
- InstagramとXだけをしっかり運用する
- 長尺のYouTube動画+その要約をLINEで流す
- Podcast音声とブログ記事の2軸に絞る
など、情報の特性やお店のスタイルに合った展開を選ぶだけでも、十分に「広がりのある発信」になります。
「再利用しやすいコンテンツ」を意識しておく
どんな形であっても、最初の“原液コンテンツ”がしっかりしていれば、その後の展開は楽になります。
- 「見出しを口に出しながら話す」
- 「3つのポイントで話をまとめる」
- 「最初に結論を伝えてから理由を説明する」
といった構成を意識しておくだけで、あとから文字起こししても読みやすく、SNS用の要約にも使いやすい素材になります。
少人数でも回せる仕組みにする
コンテンツリパーパスの本質は、「ネタを増やす」のではなく「同じネタを無駄なく回す」という考え方です。
撮影・録音した素材を、AIやテンプレを使って簡単に変換し、それを必要なSNSに載せる。
このサイクルをシンプルに回すことで、1人また少人数でも無理なく発信力を維持できます。
まとめ|コンテンツリパーパスで「少ない労力で広く届ける」発信戦略を
SNS時代の情報発信は、「数をこなす」から「賢く回す」へと進化しています。
毎日ネタを考えて、媒体ごとに別々の投稿をするやり方では、忙しいお店や個人事業主にとって到底続きません。
今回紹介した コンテンツリパーパス の考え方を使えば、
たった1つのネタを起点に、複数のSNSへ展開できるようになります。
- 長尺の動画や音声を一つ作れば、それをもとにブログ・X(旧Twitter)・Instagram・TikTok・YouTube・Podcast・LINEなど、多方面へ発信可能
- 「1ネタ7展開」をベースに、店舗やビジネスのスタイルに合わせてSNSを取捨選択できる
- AIツールやテンプレを使えば、下書きの作成や編集の手間も大幅に減らせる
大事なのは、完璧を目指さないことと、仕組みとしてルーティン化すること。
最初からすべての媒体を網羅しなくても構いません。まずは自分がよく使っている SNS を2つほど選び、「母コンテンツ→要約・切り出し→投稿」の流れを試してみてください。
情報発信に悩む店舗オーナーや個人事業主にとって、コンテンツリパーパスは “量産疲れ” から抜け出し、発信を続けるための現実的な処方箋です。
これからの時代は、「何を言うか」ももちろん大事ですが、「どう届けるか」がますます問われるようになります。
その第一歩として、今日話した10分間の内容を、1本のブログ・1つのショート動画・1つの投稿文に変えてみるところから、ぜひ始めてみてください。