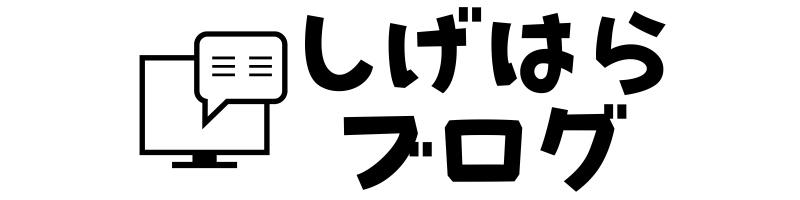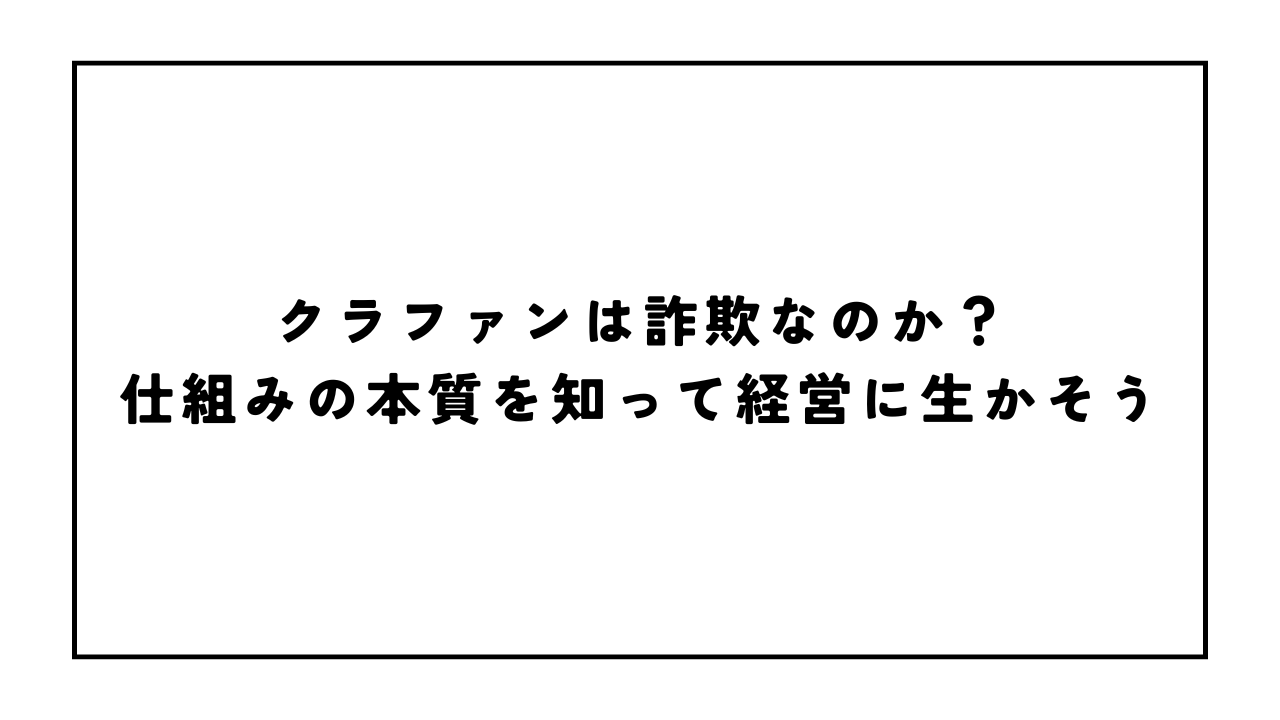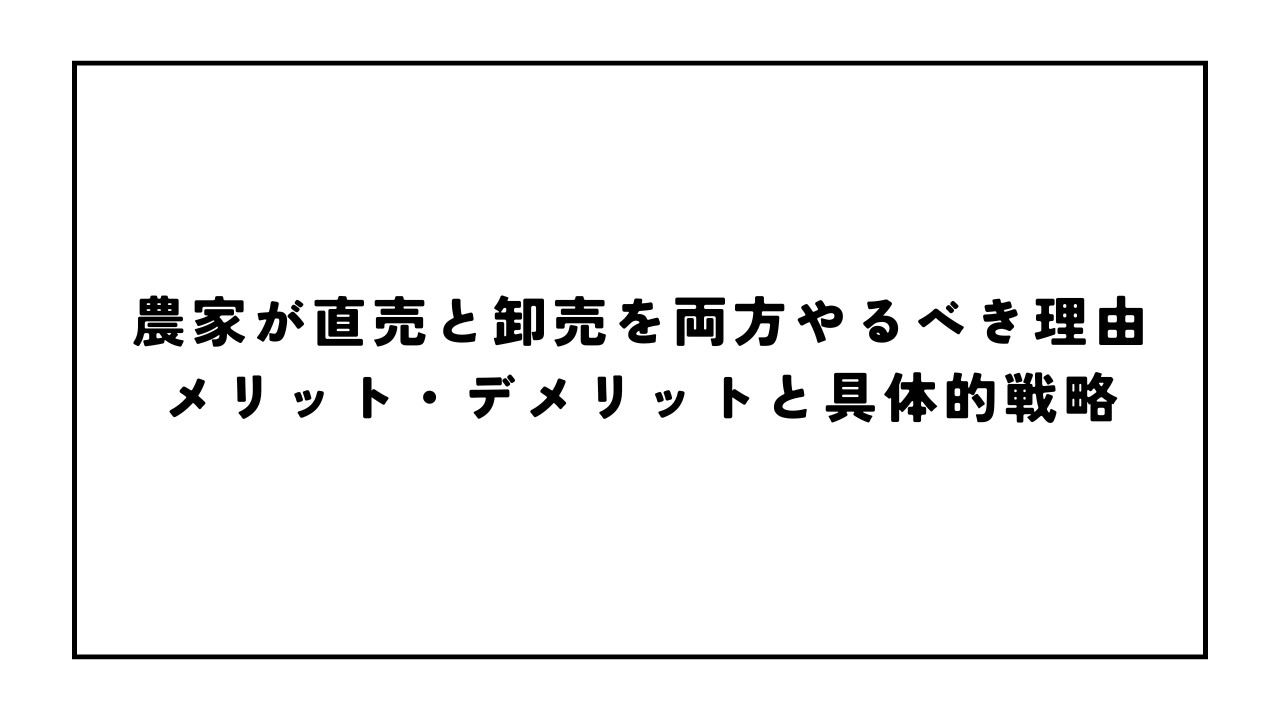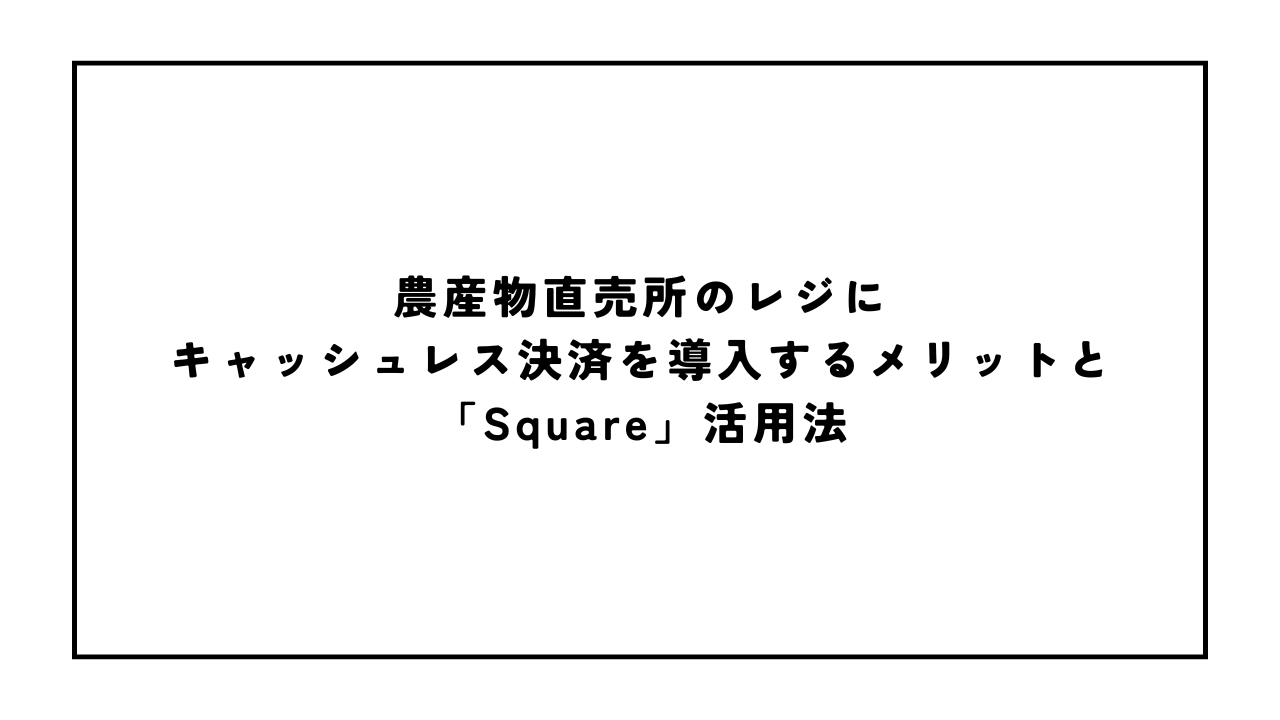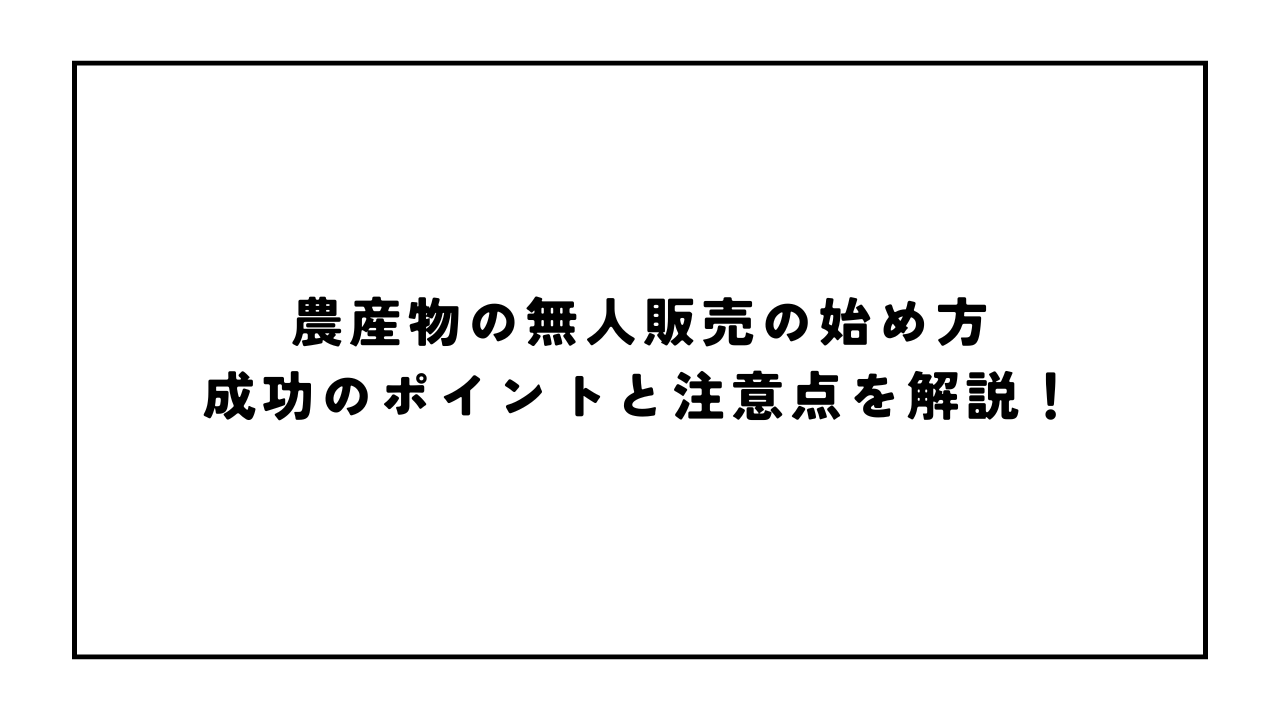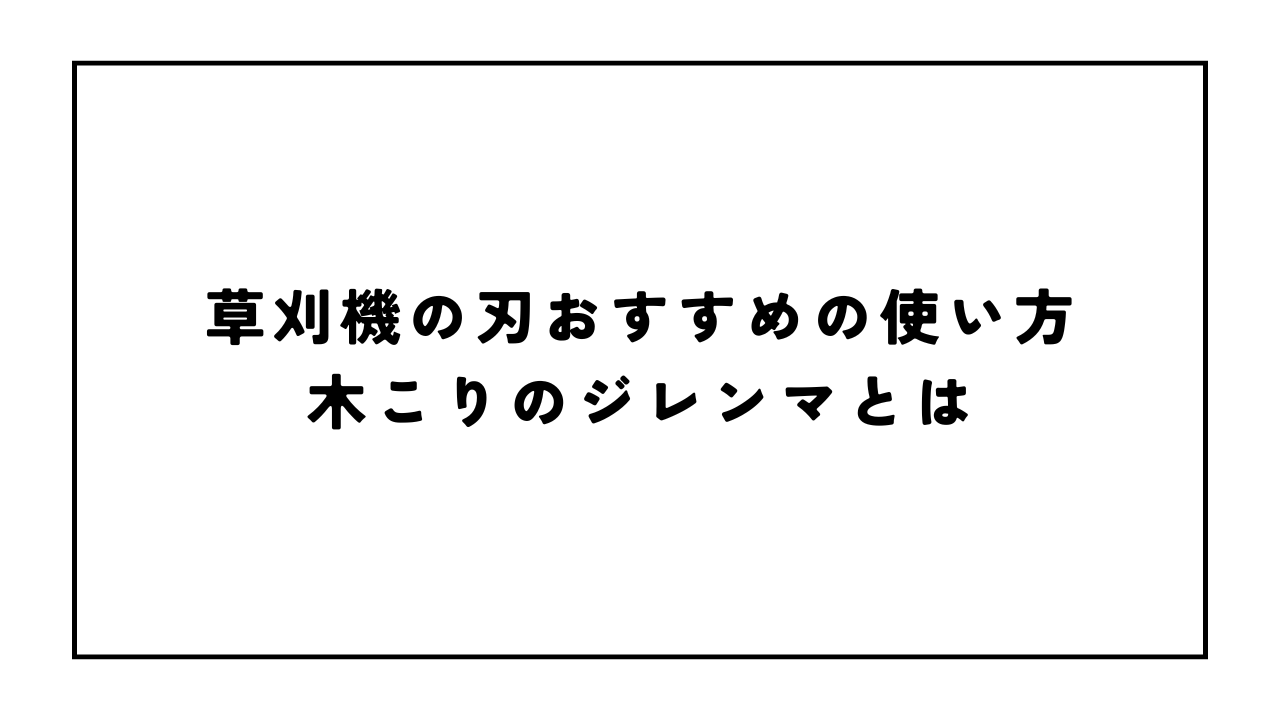農業と子育てを両立!自然の中で育む家族の幸せな暮らし
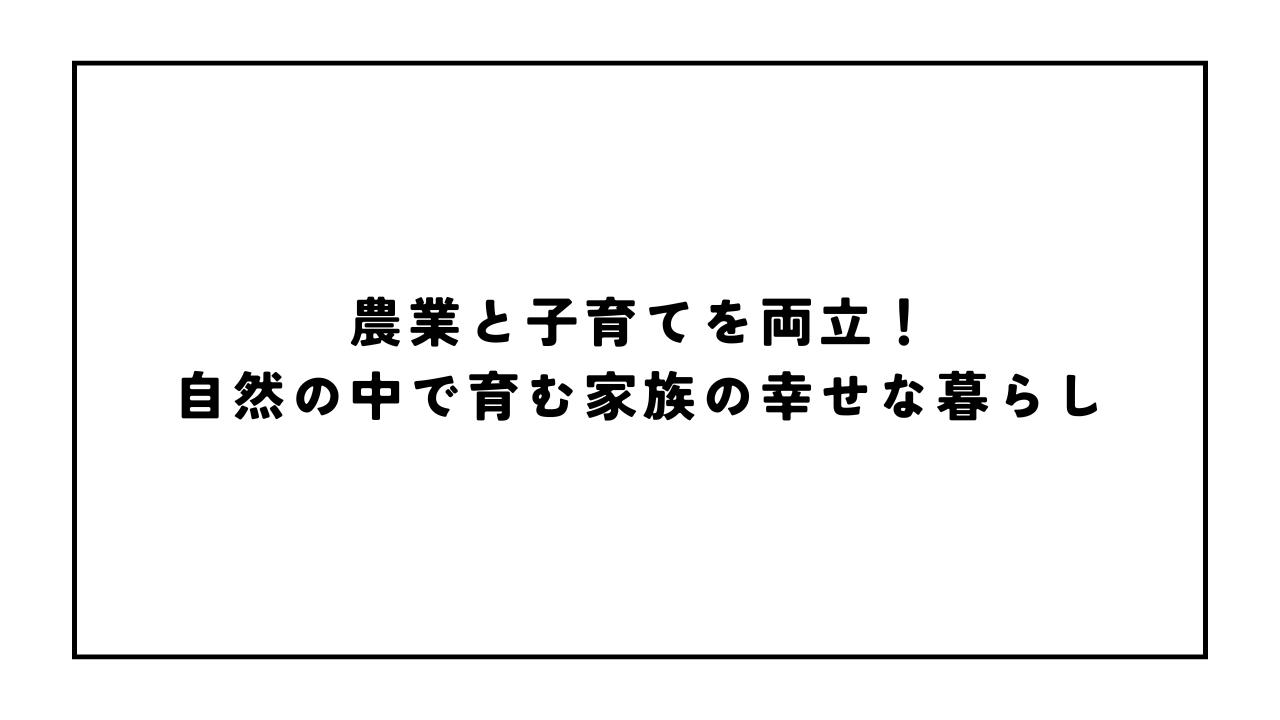
自然豊かな環境でのびのびと子どもを育てたいと考える人は多いと思います。
特に、コロナ禍以降、リモートワークの普及や地方移住の流れもあり、農業を始める若い世代が注目されています。
農業と子育てを両立することには、多くの魅力があります。
たとえば、自然の中でのびのびと育つことで、子どもは豊かな経験が出来、健康的な生活を送ることができます。
また、食育の面でも野菜や果物の栽培を身近に見て学ぶことで、食べ物のありがたみを実感することができます。
さらに、家族全員で農作業をしたり、親の仕事をまじかで見ることで親子の絆が深まり、働くことへの興味が沸くかもしれません。
本記事では、農業と子育てを両立するメリットや、実際に取り組む際の課題と対策について詳しく解説します。
農業と子育てを両立するメリット
自然の中で育つ子どもへの良い影響
五感を育む環境
農業を営む家庭では、子どもが自然の中で育つ機会が多くなります。
畑や田んぼ、山や川など、都会ではなかなか体験できない環境が広がっています。
たくさんの植物や昆虫に触れたり、農作物の栽培を近くで観察することで都会よりも五感を育むことに繋がるかもしれません。
健康的な生活習慣
農業を仕事にすることはハードワークになることもありますが、早寝早起きになり運動不足にもなりにくいです。
子供も親に習い似たような生活サイクルになりやすいと思います。
新鮮な農産物が安価で手に入りやすい事は健康面でもプラスです。
食育ができる環境
野菜や果物の栽培を学ぶ機会
農業をしていると、子どもが自然と野菜や果物の栽培に興味を持つようになります。
- 種まきから収穫までの流れを体験できる
- 植物の成長過程を学びながら、生命の大切さを知る
- 野菜や果物の旬を学ぶことで、季節の移り変わりを実感できる
実際に自分で育てた作物を収穫することで、食べ物への関心が高まり、「好き嫌いが減った」「野菜を進んで食べるようになった」という声も多く聞かれます。
畑や田んぼが身近にあることは食へ関心を持つ貴重な環境だと言えると思います。
食べ物のありがたみを実感
スーパーで買った野菜を食べるだけでは、食べ物がどのように作られ、どれだけの手間がかかっているのかを実感することは難しいです。
しかし、農業を通じて親や自分で育てた野菜を食べることで、食べ物のありがたみを深く理解できるようになります。
- 「野菜が育つには時間がかかること」を学ぶ
- 「農作業の大変さ」を知ることで、食べ物を無駄にしなくなる
- 収穫した野菜を家族で調理し、食事を楽しむことで、食卓の会話が増える
こうした経験は、子どもの成長にとって貴重な学びとなります。
家族の時間を大切にできる
子供行事参加しやすい
農業は休みが自由に取りにくい面もありますが、短時間の子供の行事に参加しやすい面もあります。
サラリーマン家庭であれば夫婦どちらかに任せてしまう平日のちょっとした行事にも参加できます。
早朝仕事をし子供を幼稚園に送っていきまた仕事に戻るなんてことも出来ます。
こうした経験を積み重ねることで、親子の絆がより深まります。
親の仕事を知れる
農業は家の近くの畑や倉庫で仕事することもあるので、身近に親の仕事を感じる事が出来ます。
簡単な作業を一緒にやったりすることも出来るので、仕事体験になります。
親への尊敬になったり、家族のコミュニケーションを深めることにつながると思います。
農業と子育てを両立するための課題と対策
忙しい農作業と子育ての時間管理
農作業は季節ごとに忙しさが異なり、繁忙期は朝から晩まで働くこともあります。
そんな中で、子育ての時間をどう確保するかが大きな課題になります。
スケジュール管理のコツ
- 作業の見える化:夫婦で農業しない場合でも、農作業と育児の予定を共有する。
- ルーティンの確立:決まった時間に子どもと過ごす時間を設定し、日々の習慣にする。出荷のない日にやすみを設定したり、朝夕の送り迎えの時間は農作業をしないようにするなど。
- 優先順位を決める:すべてを完璧にこなすのではなく、優先すべきことに集中する。農業も子育ても完璧には出来ません。
仕事と育児の役割分担
- 夫婦や家族で協力する:どちらか一方に負担が偏らないよう、家事や育児の分担を決める。農家の場合、季節によって分担を見直していく事も大切です。
- 地域のサポートを活用する:近隣の子育て支援サービスや保育施設を利用し、負担を軽減する。繁忙期は土日の保育や学童を活用することを検討しましょう。
収入の不安定さへの対策
農業は天候や市場価格に左右されるため、収入が不安定になりやすいのが現実です。
特に子育て世代にとっては、安定した生活基盤を確保することが重要です。
農業以外の収入源を持つ
- 兼業農家として働く:農業だけでなく、パートタイムやリモートワークなどで副収入を得る。また夫婦のうちどちらかは勤める。
- ネット販売:移住して農家になる場合、以前のコミュニティーへの販売も強みになります。
- 作業受託する:地方の農家は高齢化で農作業に苦労しています。そういった農家の作業を請け負うことで収入に繋がります。
助成金や補助制度の活用
新規就農者向けの補助金も充実していますし、移住の補助金もあったりします。
行政に相談することで住居や農地の紹介を受けられる可能性もあります。
子どもの預け先や教育環境の問題
農村部では保育施設や学校の選択肢が限られることがあり、子どもの教育環境をどう整えるかが課題になります。
居住地選びのポイント
農業面の産地選びと同時に保育園、学校の環境や将来高校、大学に通えるか、選択肢があるかを十分考える必要もあります。
農業と子育てを両立するうえで場所選びは最も重要なポイントと言えます。
地方ならではの教育プログラム
地方の小学校では特別な課外授業に取り組んでいる場合もあります。
私の地域ではいろいろな農家さんに取材にいく授業があります。
こういった環境は教育にもプラスの要素と言えます。
先輩農家の子育て体験談
農業と子育てを両立している家庭には、それぞれの工夫や経験があります。ここでは、実際に農業を営みながら子育てをしている家庭の体験談を紹介します。
事例1:夫婦で農業、季節でメリハリ
Aさん夫妻は、梨、ブドウの果樹栽培を行っています。
夫婦で農作業をしながら子育てしています。
果樹は季節により仕事量に大きく差があるので繁忙期は土日も子供を保育所に預けながら農作業しています。
反対に冬の時期は時間を取れるので家族で旅行に行ったりと1年間の中でメリハリをつけた生活を送っています。
- ポイント
- 夫婦で農業をし季節でメリハリのある生活。
- 繁忙期は土日も保育所を利用
- 冬は旅行など家族中心の生活
事例2:夫婦で兼業し収入を安定
Bさん夫婦は旦那さんが単身で小規模野菜農業を営んでおり、奥さんは正社員として働いています。
不安定な農業収入の不安は、奥さんのサラリーマン収入でカバーしています。
家事育児の面は自由の利く旦那さんが多く行っているそうです。
日曜日は家族の時間としてお子さんと過ごしています。
- ポイント
- 夫婦での兼業をし収入を安定させている
- 旦那さんが家事育児を多めに分担
- 日曜日が家族の時間
このようにそれぞれの家庭でいろいろな形を作農業作ることが農業と子育てを両立させるコツです。
これから農業をしながら子育てをしたい人へのアドバイス
農業と子育ての両立を目指す方に向けて、無理なく実践できる方法を紹介します。
スモールスタートで無理なく始める
農業は事業です。いきなり始めず十分に情報収集したり、小さく始める事が重要です。移住する場合も土日だけ滞在するなどから始めましょう。
- いきなり本格的な農業を始めるのではなく、家庭菜園や農業体験に参加するなどしてスタート。
- 初期投資を抑えつつ、収益モデル、作物、居住地を模索する。
- 週末農業や副業としての農業も検討する。
夫婦や家族で協力することの重要性
農業と子育てを両立するには夫婦や家族の協力は不可欠です。
一人で決めずによく相談しながら進めましょう。
- 夫婦間で役割を明確にし、お互いにサポートできる環境を作る。
- 家族と話し合いながら、農業と子育ての両立プランを立てる。
- 両親や親戚に協力を求める
地域のサポートやネットワークを活用する
- 新規就農や移住には行政の支援を検討する
- 近隣の農家や子育て仲間と情報交換をすることで、孤立を防ぐ。
- 移住体験イベントなどに参加し、実際に子どもと地方の相性を確認。
よくある質問(FAQ)
Q1. 農業をしながらの子育ては難しい?
→ 仕事と育児のバランスをとることが重要。1年の中でメリハリを付けたり、意識して子供との時間を作る必要がある。それぞれの家庭の良い形を探すことで充実した生活に繋がる。
Q2. 収入面での不安はどうすればいい?
→ 夫婦で兼業したり、農産物以外の収入を得ることで不安が減る。新規就農や移住には補助金があるので調べて活用する。小さく始める事が大切。
Q3. 子どもの教育環境は大丈夫?
→ 居住地選びがとても重要。農業経営、子育て、教育環境でバランスの取れた場所選びが必要。行政への相談や先輩子育て農家に話を聞くべき
まとめ
農業と子育ての両立には課題もたくさんあるが、それぞれの形を模索することで理想の生活に近づけると思います。
子育てにおいては自然豊かな環境や食育面、親の仕事を身近に感じられるなどメリットも多いと言えます。
移住や新規就農は行政が支援してくれることも多いので、相談に行ったり補助金を受けたりしましょう。
理想だけで突き進まず、先輩子育て農家に相談したり、短期の体験をするなど小さく試してスタートさせましょう。