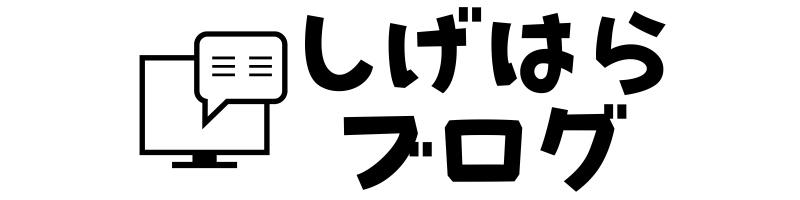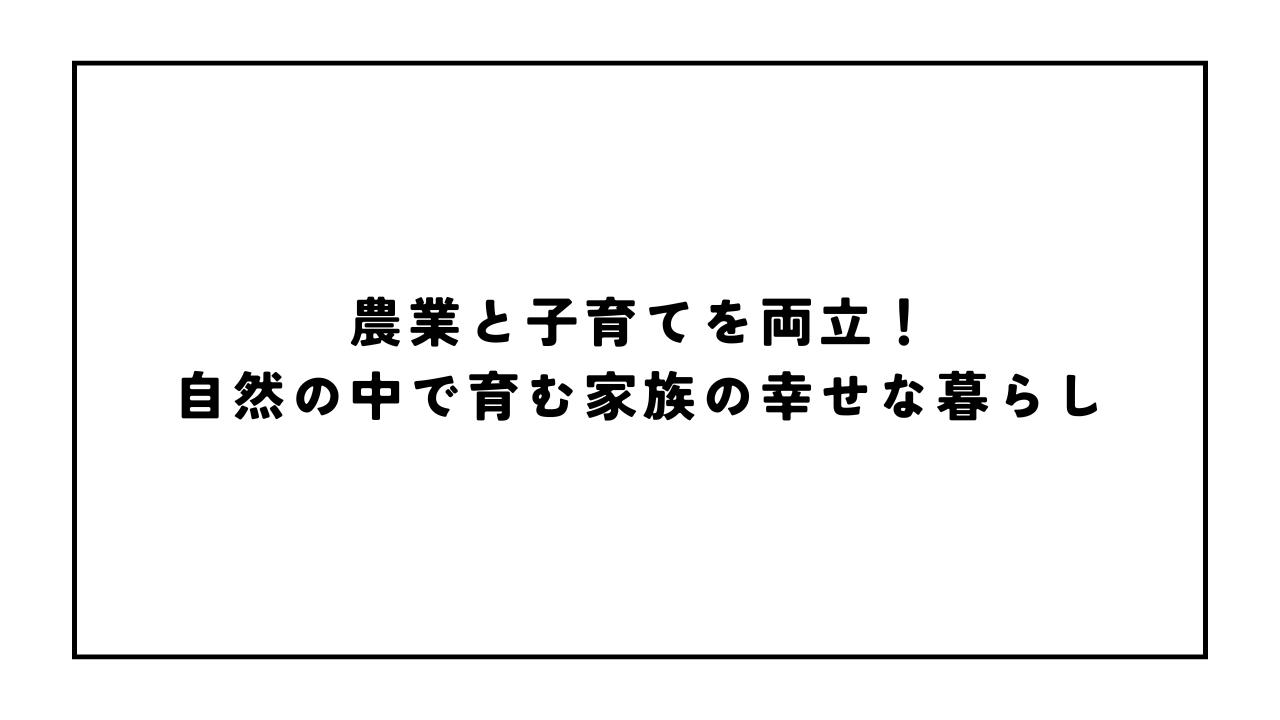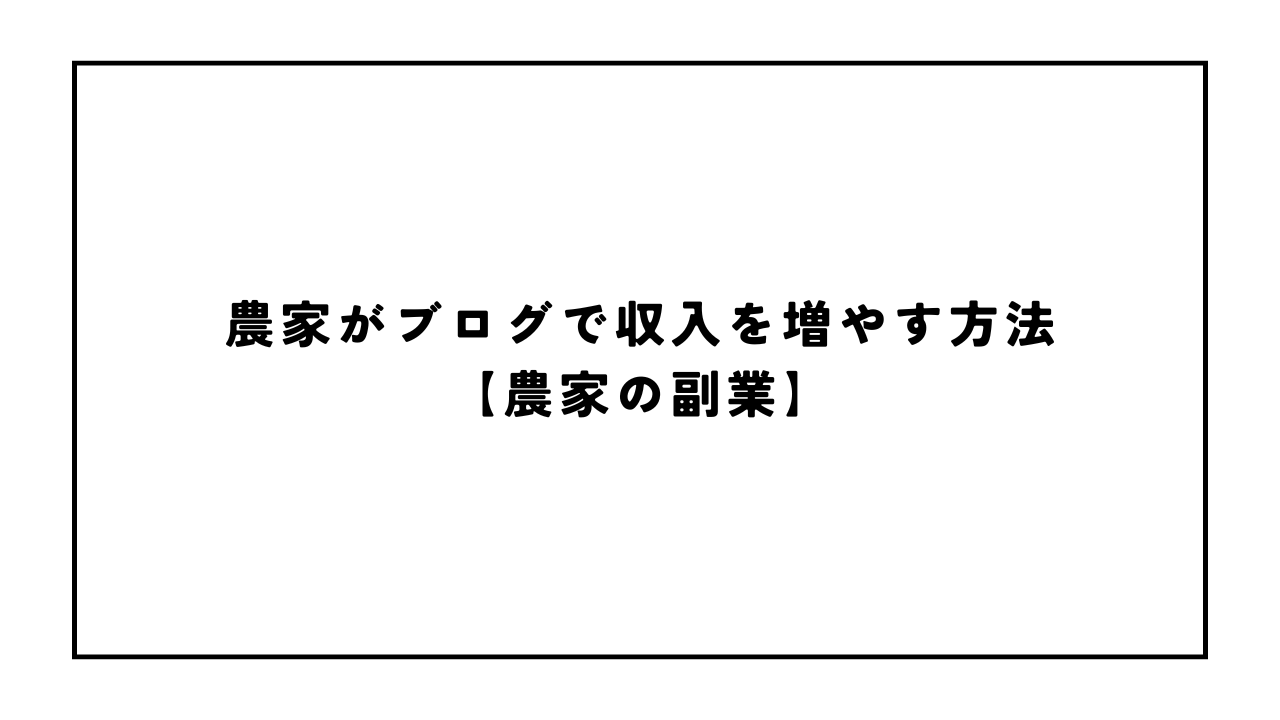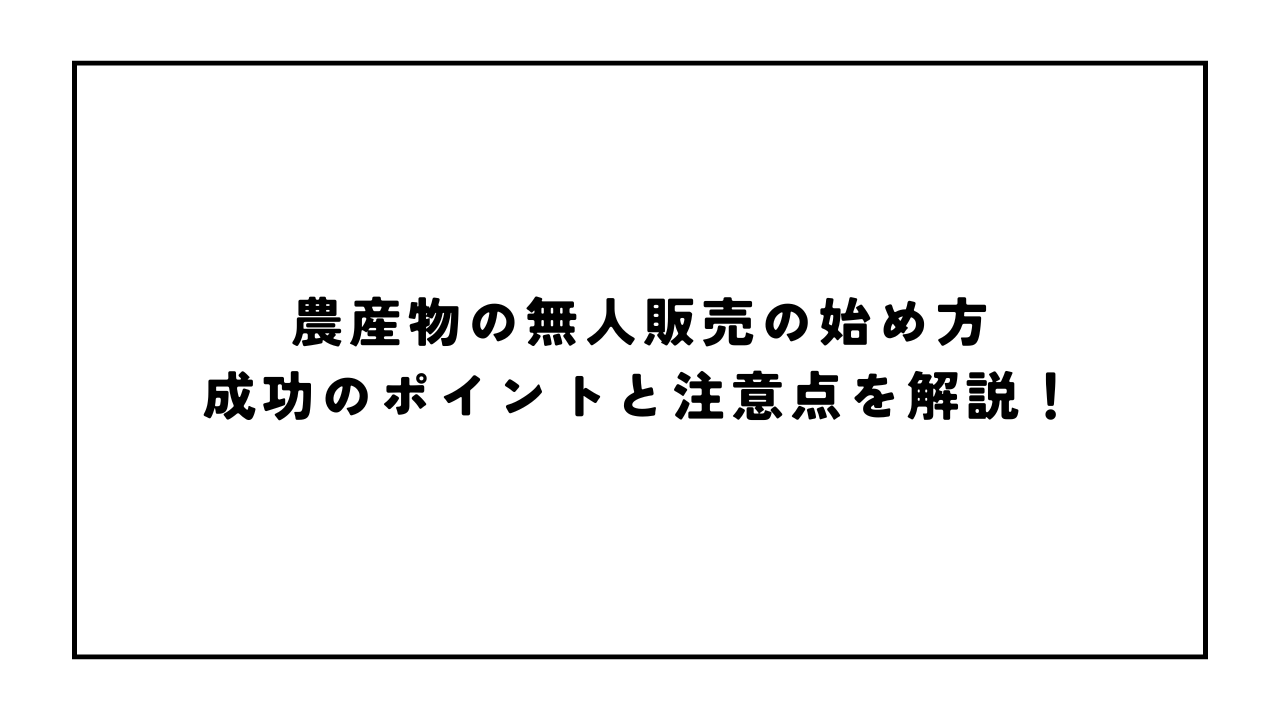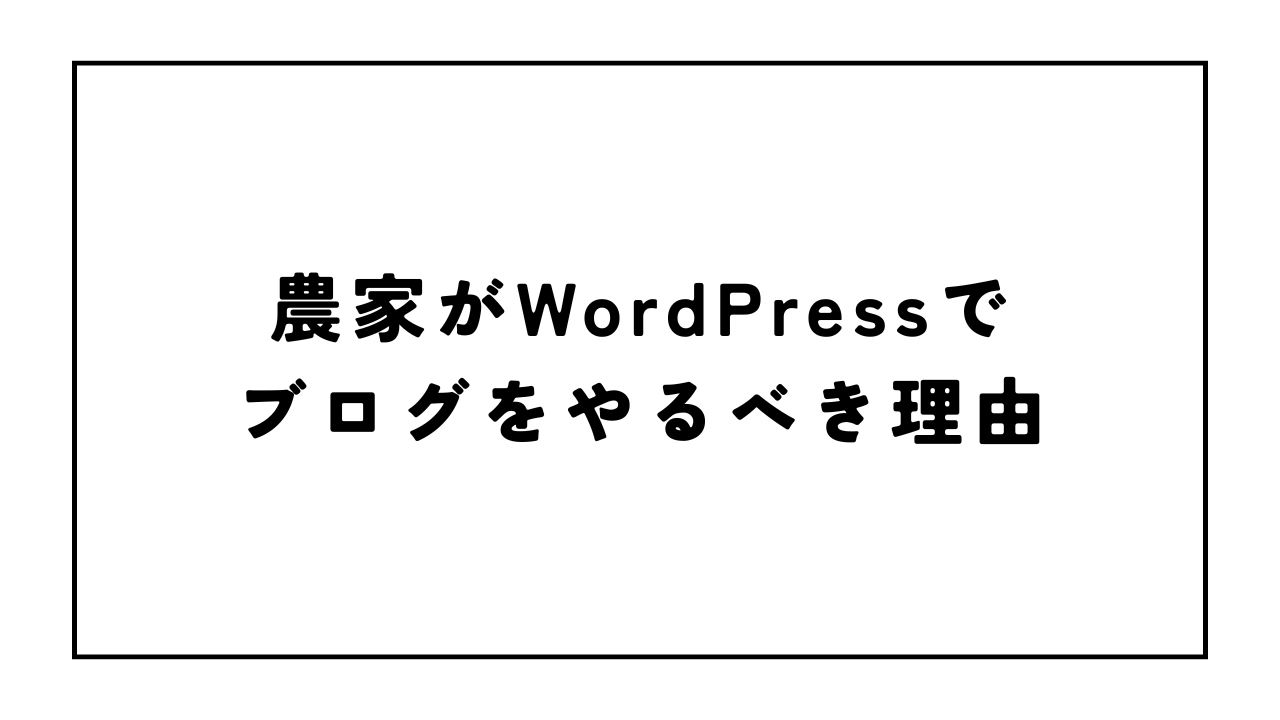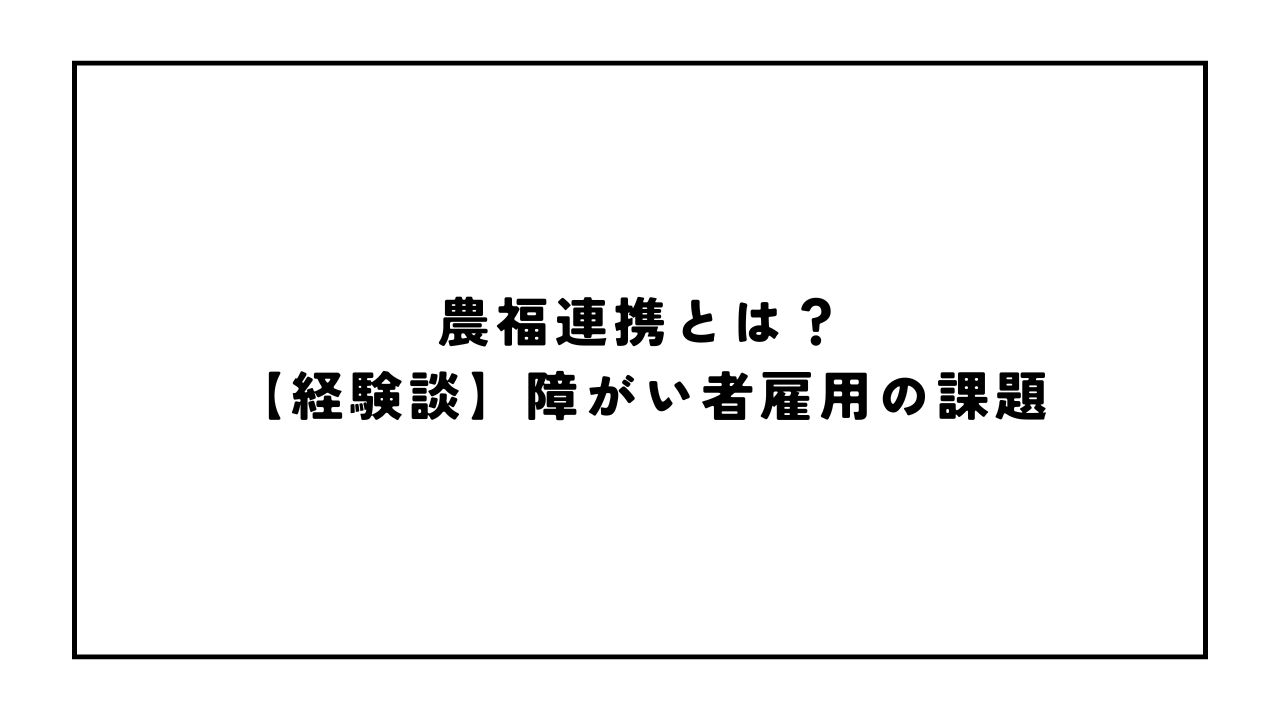農家になるには?成功するための最短ルートは“研修”にあり!
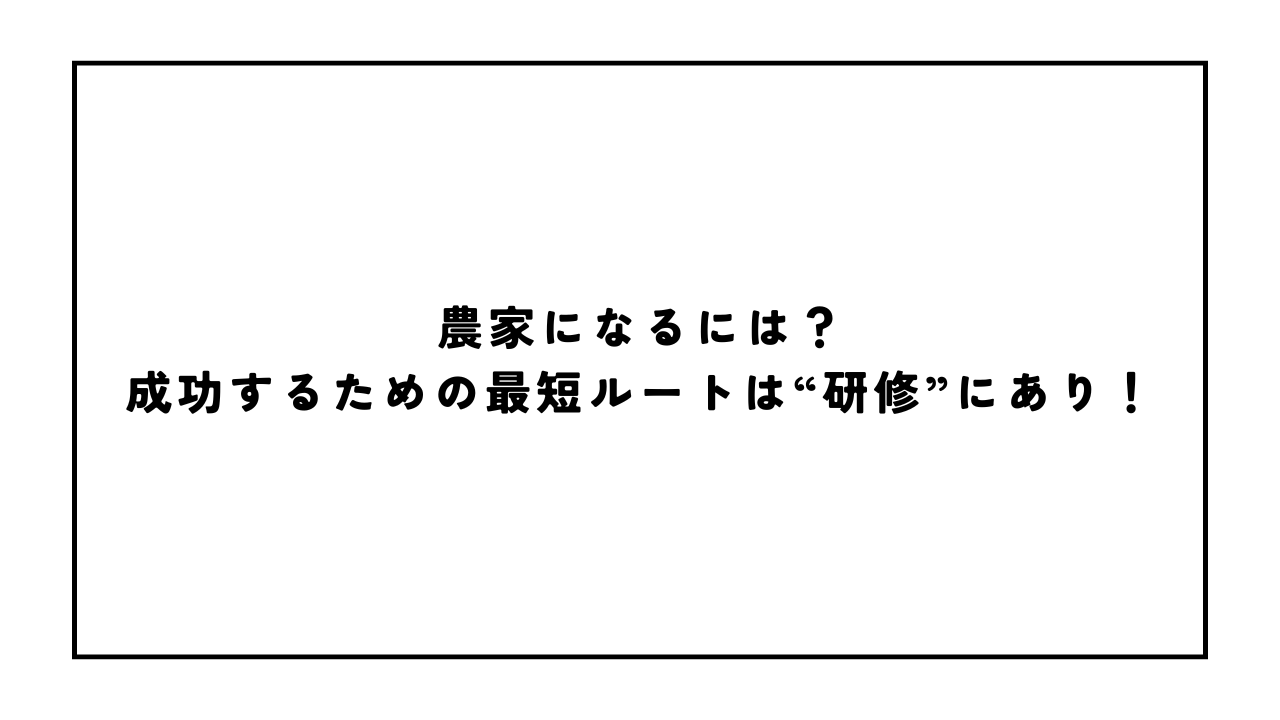
農家になるには大きく分けて3つの方法があります。
新規参入・雇用就農・親元就農 です。
新たに起業し農業を始める新規参入。
農業法人に勤める形の雇用就農。
親の元で農業をする親元就農。
農家になると言ってもいろいろなパターンがありますが。
今回は農家出身でない方が新たに新規参入で独立して農家になることを目指す方に向けて成功するためのポイントを書いていきます。
1. 農家になるためのステップ
農業未経験者が新規参入で成功するには、計画的にステップを踏むことが不可欠です。
農業は単なる作物栽培ではなく、経営・販売・資金調達など、総合的なスキルが求められます。
ここでは、農家として独立するまでの流れを詳しく解説します。あくまでも一例です。
- 就農について知る(情報収集)
- 農作業を体験する(農業体験・短期研修)
- 農業をする地域・作物を決める
- 就農窓口に相談する
- 研修を受ける(最低1〜2年)
- 農地・機械・資金を確保する
① 就農について知る(情報収集)
まずは、農業について幅広く情報を集めましょう。農業には作物の栽培だけでなく、販売や経営など多くの要素が関わってきます。
農業の現実を知る
- 日本の農業の現状(高齢化・後継者不足・農業政策など)
- 農業のメリット・デメリット(自由な働き方 と収入の不安定さ)
- 自分に向いている農業スタイルを考える
情報収集の方法
- 農水省の「農業をはじめる.jp」で基礎知識を学ぶ
- 農業イベント・自治体の就農セミナーなどに参加して経験者の話を聞く
② 農作業を体験する(農業体験・短期研修)
「農業をやりたい!」と思っても、実際の農作業をしてみると想像以上にきつかったりイメージと違うことも多いです。
いきなり独立するのではなく、まずは短期の農業体験や研修に参加して、自分に合っているか確かめることが大切です。
行政も近年はいきなりの長期研修よりも短期の体験、研修から始める事を進めています。
農業体験の方法
- 自治体主催の農業インターン(短期で農業を体験できるプログラム)
- 農業法人や農家でのアルバイト(実際の農作業を経験)
③ 農業をする地域・作物を決める
次に、自分がどこでどんな作物を栽培するか決めます。
地域選びのポイント
- 気候・土壌の条件(育てたい作物に適した土地か)
- 支援制度の充実度(自治体ごとに助成金やサポートが異なる)
- 販路の確保がしやすいか(直売所・市場・流通の状況)
- 生活(家族)とのバランス
作物選びのポイント
- 収益性が高い作物か?(市場価格・需要の変動を考慮)
- 育てやすい作物か?(初心者向きか、専門知識が必要か)
- 販路が確保しやすいか?(JA、市場・直売所・ネット販売など)
④ 就農窓口に相談する
就農を本格的に考えたら、自治体の就農窓口や農業支援機関に相談しましょう。
相談できる内容
- 就農支援制度(補助金・助成金)の案内
- 農地の紹介(農地バンクなど)
- 研修先の紹介
主な相談窓口
- 全国新規就農相談センター
- 各都道府県の新規就農相談センター(地域ごとの支援制度)
- JA(農協)や農業法人(地域の農地や研修先の情報)
⑤ 研修を受ける(最低1〜2年)
ここが最も重要なステップです。
未経験から農家として成功するには、必ず経験豊富な農家のもとで研修を受けることが必要不可欠です。(詳細は「2. 研修が重要な理由」で解説)
- 栽培技術を学ぶ(作物の特性・病害虫対策・収穫のタイミング)
- 経営ノウハウを学ぶ(資金管理・販路開拓・利益を上げる方法)
- 農業機械・設備の扱いを学ぶ(トラクター・ハウス管理など)
⑥ 農地・機械・資金を確保する
研修を受けたら、独立に向けて準備を進めます。
農地の確保
- 農地バンクを利用する(各自治体の農地情報サイト)
- 地域の農家と交渉する(引退する農家から農地を譲り受ける)
機械・設備の準備
- 必要な農機具を購入 or リースする
- 中古農機具を活用する(引退する農家から譲り受ける)
資金調達
- 新規就農者向けの補助金・助成金を活用(自治体・JA・農水省)
- 日本政策金融公庫の農業ローンを利用
⑦ いよいよ就農!
すべての準備が整ったら、いよいよ農家としてスタートです。
独立後も研修先や成功している農家と常に情報交換することが大切です。
2. 研修が重要な理由
農業未経験者の中には研修なしで独立しようとする人もいますが、農家として成功するには適切な研修が必要不可欠です。
研修で学ぶものは、栽培技術のみでなく多岐にわたるからです。
なぜ研修が必須なのか?
技術の習得ができる
農業は単に作物を育てるだけではなく、天候・病害虫対策・土作りなど、多くの知識と経験が求められます。
同じ作物であっても地域によって作業の時期や回数、使う資材など大きく異なります。
実際に就農する地域で成功している農家から学ぶことが非常に重要です。
農業経営の全般を学べる
農業で成功するには、収支管理(経理)・販路開拓・コスト削減などの経営ノウハウが必要不可欠です。
これも地域によって大きく正解が異なります。
その地域で最適な仕入れ先、卸先を知ることは大きなメリットです。
農地、農機具を紹介してもらえることもある
新規就農者にとって大きなネックの2つは農地と農機具です。
近年、耕作放棄地の話をよく聞くので農地は余っているように思われますが、農業の盛んな地域の良い農地は空いていません。
新規就農者にとっては農地が良い農地か悪い農地もわかりません。
知識のないうちにいきなり購入することは危険です。
そういったことを研修先に相談したり、良い農地を紹介してもらうことがとても重要です。
またその地域の優秀な農家で研修を受ける事で、地域から信頼を得る事が出来ます。
独立後、農地を取得しやすくなったり、使わなくなった農機具を安く譲り受ける事が出来るかもしれません。
3. 良い研修先を見つける方法
農業研修は、どこで誰に学ぶかが非常に重要です。
適切な研修先を選ぶことで、独立後の成功確率が大きく変わります
研修先を間違えると「ただの労働力」として扱われ、肝心の経営や販路のノウハウを学べないこともあります。
ここでは、良い研修先を見つけるための具体的な方法とポイントを解説します。
① 研修先を選ぶ前に考えるべきポイント
研修を受ける前に、自分がどのような農業を目指すのかを整理しておきましょう。以下のポイントを考えておくと、研修先のミスマッチを防ぐことができます。
- 育てたい作物は何か(野菜・果樹・米・畜産など)
- 目指す農業スタイルは(有機農業・慣行農業・スマート農業・直売型など)
- どの地域で農業をしたいか(気候・土壌・地域の支援制度)
- 研修期間はどれくらいにするか(短期間で独立するか、じっくり学ぶか)
自分の目指す農業を明確にしておくことで、適した研修先を選びやすくなります。
② 研修先の探し方
地域の農協(JA)や自治体に相談する
農協や自治体では、新規就農者向けの支援窓口があり、研修先を紹介してもらえることがあります。
- 都道府県の新規就農支援センター(研修制度や支援情報が充実)
- 市町村の農業振興課(地域ごとの研修先を紹介してもらえる)
ただし、自治体が紹介する農家が必ずしも良い研修先とは限らないため、事前に地域農家に評判を聞くのが大切です。
SNSや農業イベントを活用する
最近では、SNS(Twitter・Instagram・YouTube)で情報発信をしている農家も多く、自分の目指す農業スタイルに近い農家を見つけることができます。
- SNSで農家の発信内容をチェックし、直接連絡を取ってみる
- 農業系YouTubeやブログで研修を受け入れている農家を探す
- 地域の直売所やマルシェで成功している農家に直接相談する
研修生を受け入れている農家を訪問する
興味のある農家が見つかったら、いきなり研修を申し込むのではなく、まずは農場見学をさせてもらうのがベストです。
- 実際の作業や農家の考え方を知る
- 研修生がどのように扱われているか確認する
- 研修後のサポートがあるかを聞く
③ 良い研修先の条件とは
研修先の農家選びは慎重に行うべきです。以下の条件を満たしている農家が理想的です。
- 単なる作業員ではなく、しっかりと指導してくれる農家
- 栽培だけでなく、経営や販路の開拓についても学べる農家
- 研修後のサポート(農地・販路の紹介など)をしてくれる農家
- 過去に研修生を受け入れた実績がある農家
見学の際には、農家の経営状況や研修生の扱いを確認することが大切です。
④ 研修先に問い合わせる際の質問リスト
研修を申し込む際には、いくつかの農家に連絡を取り、実際に話を聞くことが大切です。以下のような質問をすると、研修の質を見極めやすくなります。
- 研修の具体的な内容は(栽培・経営・販路の学びはあるか)
- 研修期間はどれくらいか(短期か長期か)
- 独立後のサポートはあるか(農地や販路の紹介など)
- 研修後に農機具や農地を安く譲ってもらえる可能性はあるか
また、実際に研修を受けた人の話を聞くと、研修の実態がよくわかります。
4. 研修中に意識すべきポイント
研修を受ける際には、ただ作業をこなすのではなく、独立後に役立つスキルを意識的に学ぶことが重要です。ここでは、研修中に意識しておくべきポイントを解説します。
① 栽培技術だけでなく、経営の視点を持つ
農業は単なる作業ではなく、経営を軌道に乗せることが最も重要です。研修中に以下のポイントを意識して学びましょう。
- 収支管理(どれくらいの経費がかかり、利益が出るのか)
- 販売戦略(どこで売っているのか、どの販路が儲かるのか)
- 仕入れ先(種苗・資材・農機具の安い仕入れ先を把握する)
ただ作業を覚えるだけでは、独立後に苦労します。経営の視点を持って学ぶことが重要です。
② 地域の農家との人脈を広げる
農業は人とのつながりが非常に重要です。研修中に地域の農家や農協と関係を築いておくことで、独立後の販路開拓や資材調達がスムーズになります。
- 研修先の農家だけでなく、周囲の農家とも交流する
- 農業イベントや直売所で人脈を広げる
- JAや農業法人の集まりに参加し、情報交換を行う
研修期間中に築いた人脈が、独立後の成功に直結することも多いです。
③ 独立後の計画を立てながら学ぶ
研修中に何を学ぶべきかを明確にし、独立後のプランを考えながら取り組むことが大切です。
- 研修終了後、どこで農地を確保するか
- どの作物を栽培し、どの販路で販売するか
- 必要な資金をどのように調達するか
研修中に独立後のシミュレーションを行い、必要なスキルを意識的に学ぶことが重要です。
可能であれば研修中に一部の畑で、実際に栽培させてもらうと良いと思います。
実際に自分で栽培してみると、たくさん問題や課題が出てきます。
研修中であればすぐに質問してり、見てもらえるので成長が早くなります。
まとめ
新規就農で成功するには、しっかりと準備を進め、研修を活用しながら経験を積むことが大切です。
農業は単なる作業ではなく、経営の視点を持つことが求められます。研修先の選び方や、研修中の学び方次第で、独立後の成否が大きく変わります。
研修中は、栽培技術だけでなく、販路の確保や経費の管理など、経営に関する知識も積極的に学びましょう。また、地域の農家とつながりを持つことで、独立後のサポートを受けやすくなります。
就農はゴールではなくスタートです。独立後も試行錯誤を続けながら、自分に合った農業の形を見つけていきましょう。