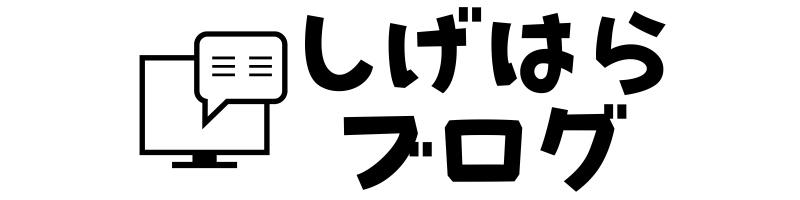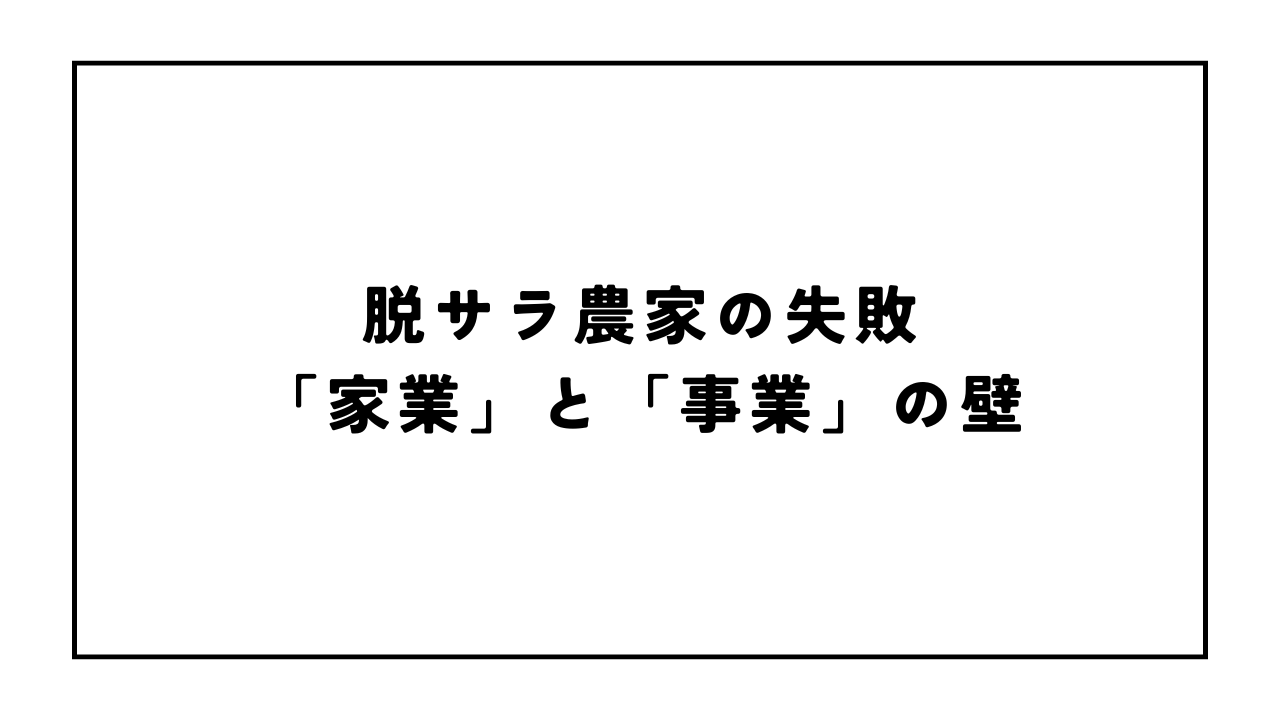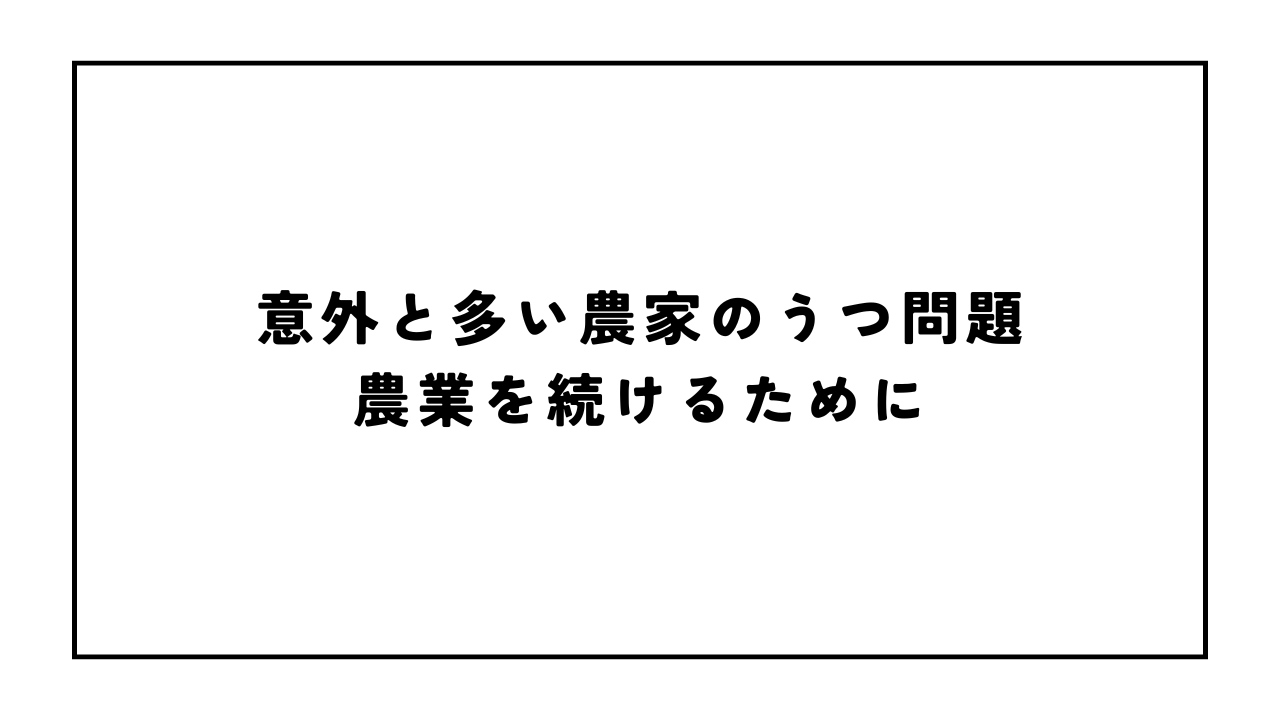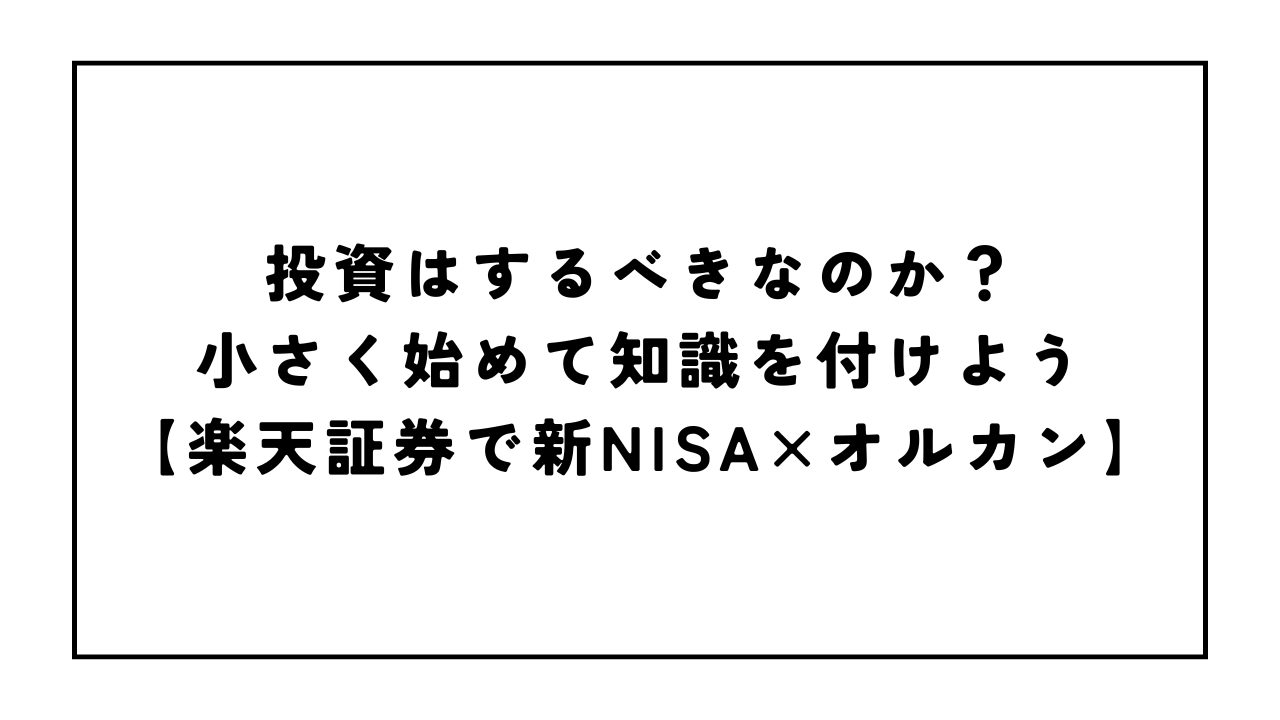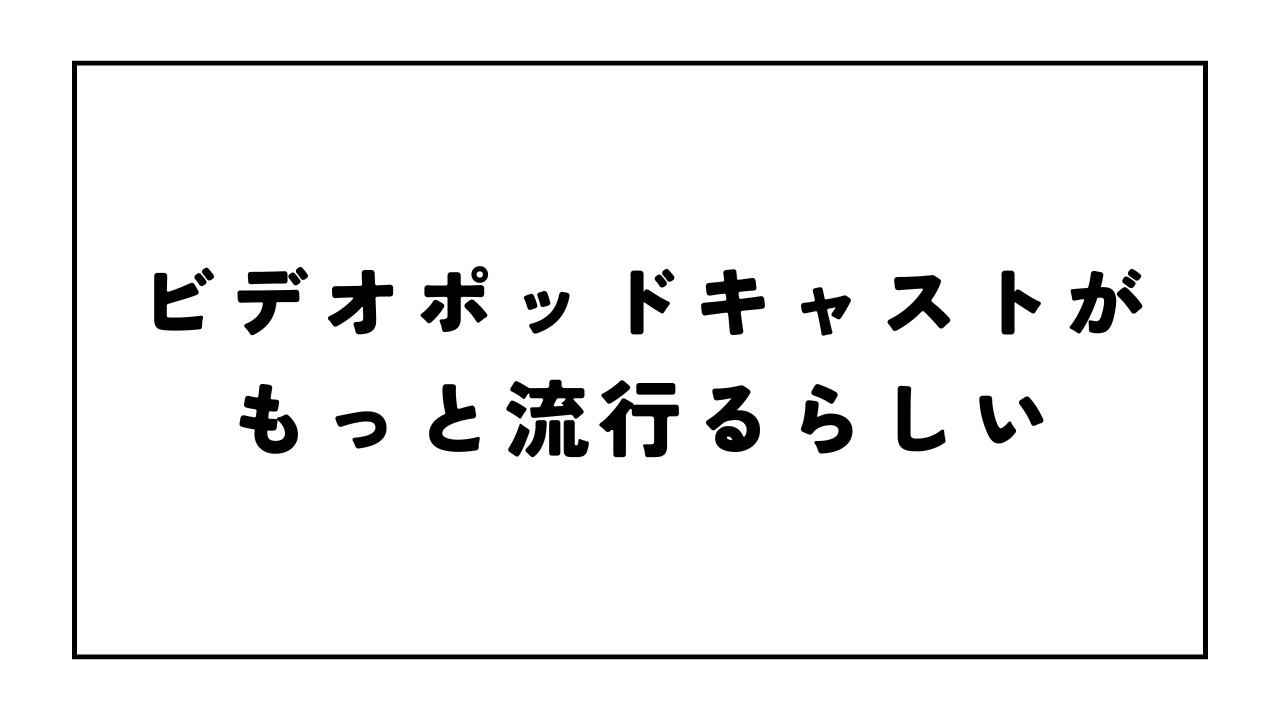スペシャリストかゼネラリストか?書籍『会社はあなたを育ててくれない』から考える人生戦略
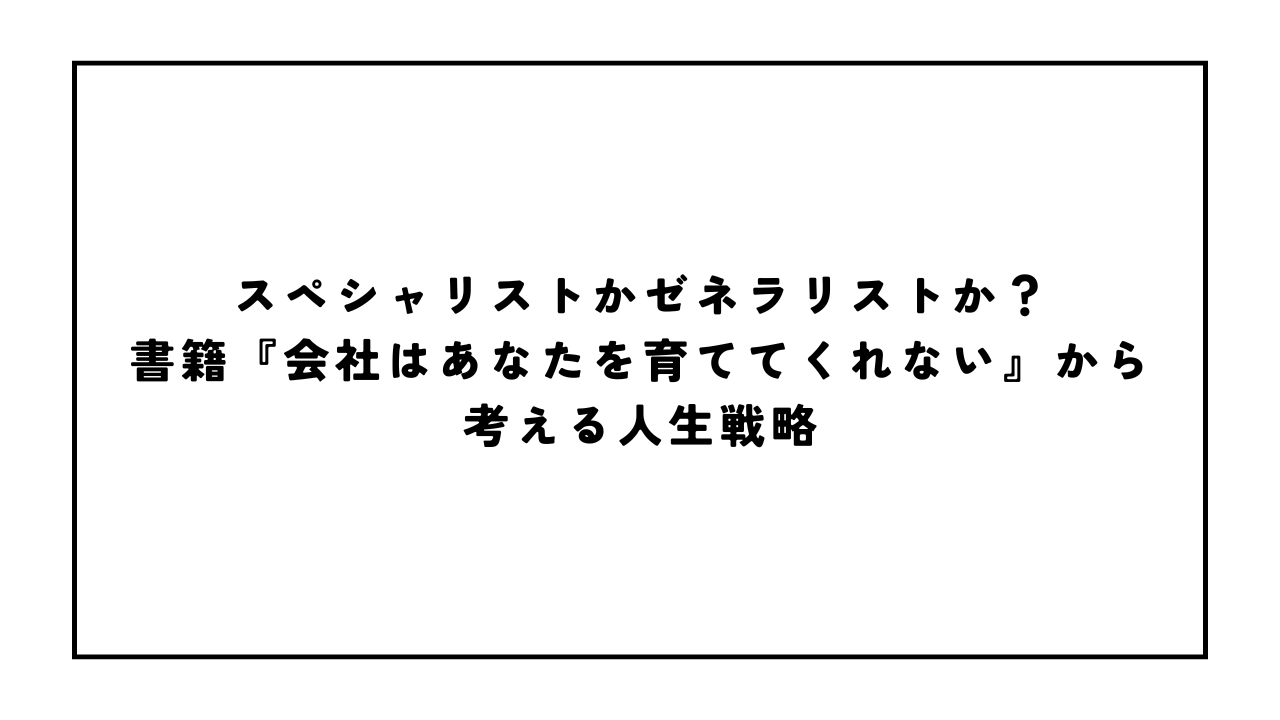
かつては「ひとつの分野を極めること」が安定したキャリアの王道とされてきました。
しかし、働き方も価値観も大きく変化したいま、「スペシャリスト」と「ゼネラリスト」どちらを目指すべきか悩む人も多いのではないでしょうか。
古屋星斗さんの著書『会社はあなたを育ててくれない』を参考に、これからの時代を生き抜くためのキャリアの設計図を考えていきます。
「近道」と「遠回り」をどう組み合わせて成長していくか、そしてAI時代におけるゼネラリストの可能性にも触れていきます。
増えたのは「自由」ではなく「選択の責任」
会社では「働き方改革」や「多様な働き方」が広まり、残業は減り、職場で怒鳴られるような場面も少なくなりました。
かつてのように、仕事一辺倒で会社にすべてを預けていればキャリアが築ける――そんな時代はもう終わりを迎えています。
一見、自由な時代に見えるかもしれません。
ですがその実態は、自分で選ばなければ何も積み上がらない時代とも言えます。
可処分時間が増えたぶん、自分に問われるもの
労働時間が減った分、プライベートに使える時間=「可処分時間」は増えました。
しかしその時間を“なんとなく消費”しているだけでは、キャリアとしての価値は積み上がりません。
- 自分はどこに向かいたいのか?
- どんな働き方・生き方を目指したいのか?
- そのために、今どんな行動をとるべきなのか?
そうした問いに向き合う時間が増えた分、選択の責任が重くなっています。
「何者かになりたい」と「自分らしくいたい」のあいだで
本書では、現代の若者に特徴的なキャリア観として、次のような2つの欲求が挙げられています。
何者かになりたい(評価されたい/成果を出したい)と自分らしくいたい(無理はしたくない/自分の感性に素直に生きたい)
この2つは矛盾しているように見えて、実はどちらも現代を生きる私たちにとって切実なものです。
だからこそ、「目指す方向は自分で決める」「そのためにどこまで力を注ぐかを設計する」必要がある。
僕自身もこの二つの感情の中で揺れています。
「自由」になったのではなく、「自分で決めなきゃいけない」環境になった――これが、現代のリアルなキャリアの出発点です。
1万時間の壁と、自分で仕掛ける成長設計
「1万時間あれば、誰でもその道のプロになれる」
この言葉を聞いたことがある人も多いかもしれません。
エリクソン教授が提唱した、あるスキルや分野で卓越するには1万時間の継続的なトレーニングが必要だというものから言われるようです。
しかし現代では、かつてよりもこの「1万時間」を積み重ねるのが難しくなっています。
昔は“勝手に”積み上がった1万時間
昭和〜平成初期までは、長時間労働や終身雇用が前提でした。
上司から言われた仕事をこなす中で、知らず知らずのうちに1万時間が“勝手に”積み重なり、いつの間にかプロフェッショナルになっていた。
でも今は、働き方改革により残業は減り、ジョブローテーションも限定的になってきた。
それに伴い、「1つの分野に腰を据えて長く働く」という環境そのものが、希少になりつつあります。
今は“意識的に”積む時代
だからこそ、現代のキャリア形成には自分で仕掛けていく視点が欠かせません。
- 興味のある分野を自分で決める
- 学ぶ時間を意識的に確保する
- 社外の活動にもスモールステップで挑戦する
こうした自発的な動きがない限り、専門性はなかなか身につかない時代になっています。
「行動に意味づけし、継続的に学ぶ姿勢」こそがキャリアをつくる土台になるというメッセージが繰り返されています。
時間がないなら、どう使うかを戦略化する
時間は減った。でも、それは悪いことだけではありません。
むしろ、自分で設計する余地が増えたとも言えます。
- 毎日30分の読書を1年続けたら?
- 週末に月1回、副業のスモールプロジェクトをやったら?
- 通勤時間に音声コンテンツで学んだら?
「1万時間」のような大きな目標ではなくても、日常の中で“仕掛ける習慣”を持てるかどうか。
それが、自分のキャリアを自分で育てていく第一歩になります。
そして余白の使い方で周りと大きく差をつけることが出来ます。
やるべきことには“近道”を。未知の可能性には“遠回り”を。
目標がある時に他の事をやることは遠回りに感じると思います。
ただ近道ばかり選んでいると自分の想像以上に広がりが出来ず、キャリアが安定しにくいと考えられます。
現代のキャリアにおいて重要なのは、「近道」と「遠回り」をかけ合わせていく事です。
「これはやるべきだ」と思えるものは、迷わず投資する
たとえば、今の仕事で求められているスキルや、自分の専門領域で価値を高めたい分野。
こうした「やるべきこと」に対しては、時間も労力も戦略的に集中投資するべきといえます。
これは“近道”です。
同時に、遠回りにも価値がある
でも、それだけでは不十分なのが今の時代。
なぜなら、“最短距離”だけを求めすぎると、視野が狭くなり、新しいチャンスに気づけなくなるからです。
これらは一見、キャリアに直接関係ない“寄り道”に思えるかもしれません。
でも、実はそこから得られる視点・人脈・経験値こそが、のちに思わぬ形で自分の武器になることがあります。
「近道」と「遠回り」を戦略的にかけ合わせる
つまり理想的なのは、「これはやる」と決めたことに対しては最短距離で取り組みつつ、
その周囲に“好奇心ベースの遠回り”を仕込んでおくというスタイル。
- メインルートで専門性を磨く(近道)
- サブルートで世界を広げる(遠回り)
これは、「一本道」ではなく「ネットワーク型キャリア」の考え方です。
キャリアの枝をあちこちに伸ばしておくことで、未来の自分に選択肢を残すことができるのです。
スペシャリスト×ゼネラリストの“かけ算”がキャリアを強くする
昔は「スペシャリストを目指すべきか? ゼネラリストでいるべきか?」という議論が主流でした。
でも今はもう、その二択自体が古くなりつつあると感じます。
求められているのは、「どちらか」ではなく「どちらも」持つ人材です。
つまり、“かけ算”のキャリアをつくるという考え方。
専門性の「深さ」× 越境経験の「広さ」
- スペシャリスト ひとつの分野を掘り下げて他にはない価値を提供する。
- ゼネラリスト 複数の分野を横断して組み合わせる力を持っている。
たとえば、マーケティング×農業、プログラミング×教育、AI×介護――
このように異なる分野を組み合わせることで、“自分だけのポジション”を築くことができるのです。
一本柱のスペシャリストに、横軸となるゼネラリスト的視点を加えることで、応用力や柔軟性、希少性が一気に高まる。
AI時代、ゼネラリストに追い風が吹いている
特に今、AIの台頭によって「ゼネラリスト的な強み」が活きる場面が急増しています。
なぜなら、かつては専門家しか扱えなかったツールや知識に、誰でもアクセスできるようになってきたからです。
- コーディング → ノーコードやChatGPTが補完
- デザイン → CanvaやAI画像生成ツールで非デザイナーも活躍
- ライティング → 構成・校正・アイデア出しもAIが手伝ってくれる
つまり、「ひとつの専門を極めなければ何もできない」という時代から、
“幅広く知っていて、それをどう組み合わせるか”で価値を生み出す時代へと変化しているのです。
ゼネラリストは「スキルを育てやすい」時代になった
AIやツールの進化によって、ゼネラリストが「仮の専門家」としてすぐに試せる土壌が整っています。
- 新しいことを学ぶハードルが低くなった
- トライ&エラーのコストも小さい
- SNSやポートフォリオで発信すれば、価値を証明しやすくなった
つまり、「まずやってみる」「試しに触れてみる」といった遠回り的行動が、すぐに近道へとつながる可能性が広がっているということです。
器用貧乏になりがちだったゼネラリストもAIの力でスキルを拡張させることで、掛け合わせるのに十分なスキルになり得ます。
キャリアは試して、組み合わせて、進化させるものだからこそ、これからの時代においては、一本の道を深く掘る専門性(スペシャリスト思考)と、複数の道を横断して掛け算する広さ(ゼネラリスト思考)の両方を意識することで、自分のキャリアをもっと自由に、もっと強く描けるようになるのです。
キャリアデザイン × キャリアドラフト
計画と偶然の“いいとこ取り”で進む働き方
キャリアを自分でつくっていく時代において、重要になるのが「どう進むか」のスタンスです。
古屋星斗さんの著書では、それを「キャリアデザイン」と「キャリアドラフト」という2つの考え方で表現しています。
- キャリアデザイン 自分のビジョンを明確に描き、そこへ戦略的に向かっていくスタイル。
- キャリアドラフト 予期せぬ出会いや偶然の流れを受け入れ、柔軟にキャリアを築いていくスタイル。
それぞれの特徴を比較すると、以下のようになります:
| 比較項目 | キャリアデザイン | キャリアドラフト |
|---|---|---|
| アプローチ | 計画的・戦略的 | 偶然・柔軟 |
| 主な強み | ゴールに向けて一貫性のある行動ができる | チャンスに乗って新しい可能性を広げられる |
| 主な弱点 | 想定外のことに対応しづらくなる | 成り行き任せになり、方向性が曖昧になる |
| 活かされやすい場面 | 転職・スキルアップ・起業など明確な目標がある時 | 新しい人脈・副業・趣味からの転機など |
| 求められる力 | 計画力・逆算思考 | 柔軟性・好奇心・即応力 |
キャリアは計画通りにいかないからこそ、どちらかだけではなく、両方の視点を持っておくことが大切です。
たとえば、「目指す方向は自分で決める(デザイン)」、でも「途中で出会う偶然にも乗ってみる(ドラフト)」。
僕自身も、意図して進んだ道と、偶然つながった出来事の両方が、今のキャリアに生きています。
予想外の出会いや変化が、新しい選択肢や成長を連れてきてくれる──そんなことが何度もありました。
次のキャリアを考える今後もこの視点を持っていきたいと思っています。
自分の「人生ポートフォリオ」をどう組むか?
キャリアの軸を「自分で設計し、偶然も受け入れながら築いていく」
そんな柔軟な姿勢が求められる今、自分の人生そのものを“投資ポートフォリオ”のように捉える考え方が必要です。
「ひとつに全振りしない」生き方へ
かつては「仕事=人生」であり、会社に身を委ねることが安定の象徴でした。
でも今は、
- 本業
- 副業
- 家庭・育児
- 地域活動・ボランティア
- 学びや趣味 など
といった複数の役割や活動を、どう自分の人生に組み込むかが問われる時代になっています。
どれか1つに偏りすぎれば、そこが崩れたときに人生ごと不安定になる。
だからこそ、いくつかの「顔」を持ち、それぞれに適切なエネルギー配分をしていくことが重要です。
人生のバランスを取る「ポートフォリオ思考」
本書でも登場する考え方のひとつに、「コミットメント・シフト」というキーワードがあります。
これは、「一気に転職・独立するのではなく、少しずつ比重を変えていく」という発想。
- 週末だけ副業を試してみる
- 家庭との時間を意識的に確保する
- 興味のあるNPO活動に月1回だけ関わってみる
こうした小さなシフトを通じて、人生の中の“働く・暮らす・関わる”のバランスを自分なりに調整していく。
無理なく、でも着実に、「今の自分」と「なりたい自分」の距離を縮めていく行動戦略です。
まとめ:キャリアは、一本道じゃない
「スペシャリストか?ゼネラリストか?」
「近道か?遠回りか?」
「計画か?偶然か?」
そのどれもが、二択ではありません。
両方を“戦略的にかけ合わせていく”発想こそが、これからの時代を生き抜くカギです。
キャリアはもう、誰かが決めたルートをなぞるものではない。
自分で描いて、自分で調整して、ときにブレながらも歩き続ける人生経営そのものです。
だからこそ、「自分で考える力」と「自分で動く勇気」を少しずつでも育てていきたい。
この本を通じて、そしてこの記事を読んで、「これから」を考えるきっかけになったら嬉しいです。
僕も頑張ります。